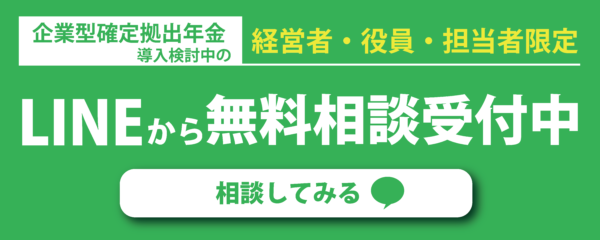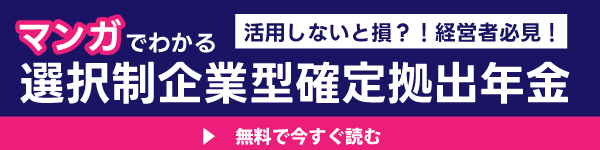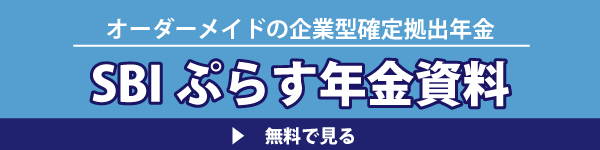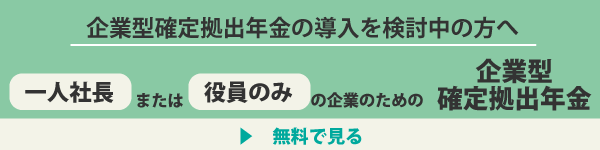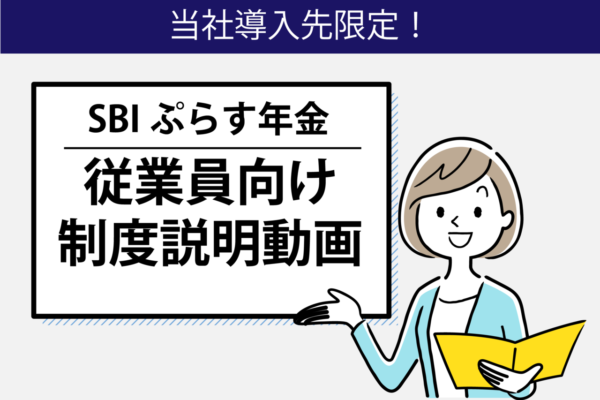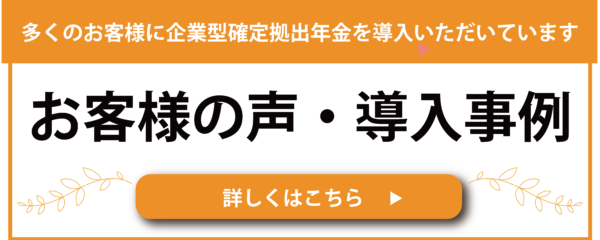よくあるご質問
ここでは「よくあるご質問」をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
目次
Q 加入者1名でも企業型を導入できますか?
A 1名からでも導入可能です。
確定拠出年金法では企業型の設立に人数要件はありません。厚生年金の適用事業所であれば導入可能です。
Q 確定拠出年金の加入者数や導入している実施事業主(所)数は?
A 企業型DCの加入者数は8,053千人です。実施事業所数は47,138社です。 ※2023年3月末時点(厚生労働省HPより)
iDeCoの加入者数は以下のとおりです。
国民年金第1号被保険者(自営業者等):362,317人
国民年金第2号被保険者(給与所得者等):2,880,478人
国民年金第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者):147,068人
国民年金任意加入被保険者:9,748人
登録事業所数は821,492事業所です。
※2024年7月末時点(iDeCo公式サイトより)
Q 役員も企業型に加入できますか?
A 60 歳未満の厚生年金保険被保険者であれば、役職に関係なく社長や役員でも加入できます。
もちろん、掛け金は全額損金計上できます。拠出限度年齢の引き上げを行った場合は拠出限度年齢まで加入できます。
例)拠出限度年齢65歳の場合 65歳未満の厚生年金被験者
Q 役員のみの企業の場合、個人型と企業型ではどちらがメリットが大きいですか?
A 税、社会保険料への影響を考えると、役員のみの加入であっても企業型のメリットは大きいと言えます。
役員が厚生年金の被保険者の場合、個人型の拠出限度額は月額23,000 円となります。一方、企業型では月額 55,000 円と 倍以上の掛金を拠出できます。さらに企業型で拠出する掛金は損金となり、個人の給与収入とはならないため、社会保険料の算定基礎からも外れます。
Q 希望する従業員のみ加入することはできますか?
A 可能です。ご希望に合わせたプランをご提案いたします。
前払退職金制度と確定拠出年金制度の選択制とすることで、希望者のみ加入が可能となります。希望しない従業員は前払退職金として給与に併せて受け取ります。
Q 社会保険料が下がることの不利益はありませんか?
A 社会保険料が下がることにより、将来支給される「老齢厚生年金」の額が減少する可能性があります。
同様の理由から、健康保険、雇用保険における給付額が減額となる可能性があります。
<計算例>加入者年齢30 歳(給与月額25 万円)が60 歳まで毎月1 万円の掛金拠出をした場合
| 保険種類 | 支給金種類 | 減額見込額※ |
| 厚生年金保険 | 老齢厚生年金 | 39,464円(1年あたり) |
| 健康保険 | 出産手当金 傷病手当金 | 477円(1日あたり) 477円(1日あたり) |
| 雇用保険 | 育児休業給付金 | 223円(育児休業開始日から180日目まで) 167円(育児休業開始日から181日目以降) ※いずれも1日あたり |
| 介護休業給付金 | 223円(1日あたり) |
※現在の法令等に基づいた概算値であり、実際の金額とは異なる場合があります。
Q 掛金の積み立てを停止することはできますか?
A 原則、掛金の積立てを停止することはできません。
ただし、休職期間、育児・介護休業期間中(共に会社都合以外の事由の場合に限る)のうち無給の期間については、規約に定めることで掛金の積立てを停止できます。
Q 年金資産の引き出しはできますか?
A 原則、途中引き出しは認められていません。
年金資産は「一定の年齢(60 歳以上)の到達」「障害の認定」「死亡」以外での、途中引き出しは原則認められていません。
Q 60歳以上の社員が企業型確定拠出年金に加入することは可能ですか?
A 厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば、加入することができます。
ただし、企業によって加入加藤年齢などが異なります。企業型確定拠出年金規約で定める資格として、「一定の年齢未満」であることを定めることができます。
そこで、60歳以上の社員が企業型確定拠出年金に加入するためには、規約にて、資格喪失年齢の延長(最長70歳)が定められている必要があります。ただし、老齢給付金の受け取りは引き上げられた資格喪失年齢に達するまでできません。
Q 個人型確定拠出年金と同時に加入する場合、現状よりも上限額は増えますか?
A 上限額は変わりません。
企業型と個人型に同時に加入した場合でも、法令上の上限額55000円に変わりありません。また、会社に企業型確定拠出年金以外の企業年金制度を導入している場合には、その上限額が27,500円となります。
【企業型と個人型に同時に加入する場合の上限額】
合算限度額55,000円 ― 企業型掛金額 = 個人型掛金額
| 企業型確定拠出年金のみ | 企業型確定拠出年金以外の企業年金制度あり | |
| 企業型掛金上限額 | 月額55,000円 | 月額27,500円 |
| 個人型掛金上限額 | 月額20,000円 | 月額12,000円 |
Q 継続的な投資教育とは何をすればいいでしょうか?
A 社員向けに説明会や勉強会を開催することが望ましいですが、「投資教育」は努力義務ですので罰則規定は設けられておりません。
弊社でも説明会の動画や一般の社員が参加できるオンラインセミナーを定期的に開催しますので、そちらに参加いただくのもいいです。
Q 個人型(iDeCo)の年金資産を企業型(企業型DC)へ移換できますか?
A 企業型DCの加入資格を取得し、企業型DCで掛金を拠出する加入者は、iDeCoの運用商品を一旦全部売却し、現金化した後に企業型へ移換できます。
なお、自身の資産を企業型DCに移換せずに個人型(iDeCo)に残して、個人型運用指図者となる事も本人の希望に応じて可能です。
Q 確定拠出年金の資産を持ち運ぶ(移換)ときには、課税されますか?
A 課税されません。加入者が中途退職したり、他の会社に就職したりなどして、他の確定拠出年金等へ移る場合は、それまで積み立てた年金資産を非課税のまま移換できます。
なお、自身の資産を企業型DCに移換せずに個人型(iDeCo)に残して、個人型運用指図者となる事も本人の希望に応じて可能です。
Q 自己破産した場合の年金資産の取り扱いを教えてください
A 確定拠出年金法では、自己破産したとしても差押することは禁止されています。
確定拠出年金法第32 条では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められており、会社破綻時に自己破産しても、最低限の老後資金を保全することができます。中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証するケースが多いため、経営者の有効な防衛手段となります。
Q 老齢給付金の請求は受給可能年齢に達した後、すぐに手続きをすべきですか?
A 受給可能となった日から75 歳の誕生日の2 日前までは、いつでもご請求可能です。
ただし、老齢給付金の請求を行わないで75 歳に達したときは、資産管理機関が記録関連運営管理機関(ぷらす年金プランであればSBIベネフィット・システムズ社)の裁定に基いて、老齢給付金の支給を行います。確定拠出年金法第32 条では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められており、会社破綻時に自己破産しても、最低限の老後資金を保全することができます。中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証するケースが多いため、経営者の有効な防衛手段となります。
Q 具体的な税制メリットについて教えてください
A 企業型確定拠出年金には3つの「税制優遇」があります。
- 掛金積み立て時の税制メリット
掛金積み立て時の会社が負担する掛金は全額損金の対象となります。掛金は個人の確定拠出年金口座に積み立てられますが、個人の所得とはみなされません。よって、所得税・住民税もかかりません。また毎月拠出する掛金は社会保険料の対象外となります。 - 掛金運用時の税制メリット
企業型確定拠出年金の運用益は非課税です。通常、金融商品を運用する場合、利子や運用益に対して、20.315%の税金がかかります。 - 年金受取時の税制メリット
一時金受取を選択した場合は退職所得として退職所得控除の対象、年金受取を選択した場合は雑所得として公的年金等控除の対象となります。
Q 選択制の確定拠出年金の掛金が社会保険料や所得税等の算定基礎とならない根拠を教えてください
A 社会保険料や所得税等の算定基礎となる所得が拠出時点では発生していないとみなされているためです。
選択制の確定拠出年金の掛金は、確定拠出年金法上「事業主掛金」と定義されます。選択制で拠出された「事業主掛金」は、所得税法施行令 64 条により会社が加入者の確定拠出年金口座に掛金を拠出しても加入者の所得とならないと規定されています。
確定拠出年金口座に拠出された掛金は加入者に財産権がある資産ですが、実際には受給権が発生する 60 歳以降まで受け取ることができません。このため、所得となるのは受給権が発生する 60 歳以降となり、それまで課税が繰り延べられます。選択制の掛金に対して社会保険料が掛からない根拠は、社会保険料の算定基礎となる所得が拠出時点では発生していないとみなされているためであり、その結果として選択制確定拠出年金においては、掛金の額によっては社会保険料が減額されることになります。
Q ポータビリティとはどのようなことですか?
A 現在加入している制度で積み立てた資産を、他の確定拠出年金制度に持ち運ぶことです。
確定拠出年金制度におけるポータビリティとは、現在加入している制度で積み立てた資産を勤務先や就業等の状況に応じて、他の確定拠出年金制度に持ち運ぶことを指します。
60 歳以降に老齢給付金が受給可能な企業型に加入している加入者が、受給年齢到達前の転職または中途退職により加入資格を喪失する場合、これまで積み立てた年金資産を転職先の企業型制度もしくは個人型に移換して運用を継続できます。
Q 確定給付型年金と確定拠出型年金の違いは?
A 大きく分けて年金には二つのタイプがあります。
一つは確定給付型であり、もう一つが確定拠出型です。
確定給付型は加入者の制度への加入期間や在職中の平均給与額などに応じてあらかじめ年金受給額が決まり、一方、確定拠出型は運用成績の良し悪しに応じて年金受給額が変動するタイプです。
日本の国民年金・厚生年金保険といった公的年金だけでなく、厚生年金基金など民間の企業年金なども確定給付型です。
Q 中小企業退職金共済(中退共)を辞めて、確定拠出年金へ移行できますか?
A 通常、移換することはできません。ただし、一部移換ができるケースがあります。
- 中小企業者でなくなった場合
中退共の加入要件である中小企業に該当しなくなった場合には、企業型確定拠出年金への移換が可能です。 - 合併等の場合
中退共制度を実施する企業と企業型確定拠出年金制度を実施する企業が合併した、2つの制度のグループがある場合には、いずれかの一方の制度に統一することができます。合併後、企業型DCのみを実施する場合には、中退共から資産を移換することができます。逆に企業型DCから中退共に資産の移換も可能です。
Q 正社員・パートタイマーといった雇用形態や勤続年数の違いで加入を制限できますか?
A 厚生年金被保険者であれば、加入要件を満たすため除外の理由になりません。
選択制企業型確定拠出年金は希望者が加入という制度設計上、入社●年目以上という縛りはできません。しかし、規約を定めて加入範囲を限定することができます。
(例:一定の職種に規定する。一定の勤続期間に資格を与える。一定の年齢の範囲に限定する。など)
Q 企業型確定拠出年金を受け取るまでに退職(転職)したらどうなるのでしょうか?
A 退職後、資産を他の確定拠出年金制度に移換する必要があります。
転職先に企業型確定拠出年金制度がある場合、転職前の企業で積み立てた資産を転職先の企業型確定拠出年金に移換することができます。
転職先に企業型確定拠出年金制度がない場合、脱退一時金を受け取る※か、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換することができます。
また、退職後、自営業を営む場合、仕事をしない場合、専業主婦になる場合、公務員になる場合もiDeCoへの移換が可能です。
ただし、退職から6か月以内に移換手続きが必要です。期限を過ぎると、年金資産は国民年金基金連合会へ自動移換されます。自動移換された場合、「管理手数料が発生する」「資産の運用ができない」「税制優遇が受けられない」等のデメリットが発生します。
※脱退一時金を受け取るには、一定の条件を満たす必要があります。
Q 運用商品の変更したい時、どのくらいの頻度で可能ですか?
A 法定上、少なくとも3ヶ月に1回の頻度で運用商品の変更をできる機会を与える必要があります。
変更する場合は、運営管理機関に変更の指示を出します。
Q 確定拠出年金の資産に対しては課税されますか?
A 年金資産には、約1.173%(法人住民税を含む)の特別法人税が課税されます。
なお、特別法人税は、現在は課税が凍結されています。
Q 運営管理機関の役割とは?
A 運営管理機関の主な業務は下記の通りです。
1. 運用関連業務
運用商品の選定・提示
提示運用商品についての情報提供
2.記録関連業務(レコード・キーピング業務)
加入者および運用指図者(以下「加入者等」といいます。)の個人資産残高・拠出金・取引履歴などの記録の保存、通知
加入者等の運用指図のとりまとめと資産管理機関への通知
給付の裁定
※弊社では、上記1,2の両業務をワンストップで提供し、より効率的な運営を可能としております。
Q 資産管理機関の役割とは?
A 一言でいえば、「掛金を企業・加入者の財産から明確に分離し、保全管理する」ということになるでしょう。
例えば、運営管理機関が取りまとめた運用指図に従い資産の運用管理を行うこと、などが挙げられます。
より制度について、詳しく知りたい方は
ぜひ無料相談をご利用ください
●自分ひとりだけ加入した場合、どのくらい節税になるの?
●うちの会社に合った企業年金制度を教えて欲しい!
●導入に関する費用はどれくらいかかるの?
どのような内容でも構いません。企業型確定拠出年金・お金の専門家がそれぞれの疑問にお答えします。また、企業状況に応じて、貴社にあった企業型確定拠出年金の制度設計方法や制度設計に合わせたメリット・デメリットを丁寧に説明さえていただきます。ぜひお問合せください。
(24時間受付中)
お電話いただければ、すぐにお応えいたします。
TEL:050-3645-9040 平日9:00~17:00(土日祝除く)
お問合せ・ご相談はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:050-3645-9040
※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。
- 投資信託の「約定日」「申込日」「受渡日」の違いは?企業型DCの影響も解説 2026年1月22日
- 資産形成とは?初心者向けの種類別解説と企業型DC・NISA活用のコツ 2026年1月21日
- インフレとは?デフレとの違いやメカニズム、老後を守る企業型DCを解説 2026年1月20日
- 所得代替率50%の罠とは?高所得者が直面する老後の現実と企業型DCによる対策 2026年1月19日
- 「国民年金基金は入ってはいけない」と言われる理由は?企業型DCとの違いも解説 2026年1月6日
- 小規模企業共済等掛金控除とは?対象の種類と企業型DCとの違いをわかりやすく解説 2026年1月5日
- 運用指図者とは?加入者との違いや切り替わるタイミング、運用のポイントを解説 2025年12月24日
- 投資信託の目論見書とは|企業型DCの信託報酬を見極めるポイント 2025年12月23日
- 企業型確定拠出年金は毎月3,000円でも効果ある?最低掛金でも始めるべき理由を解説 2025年12月22日
- こどもNISAとは?企業型DCも活用して効率よく資産形成する方法 2025年12月18日