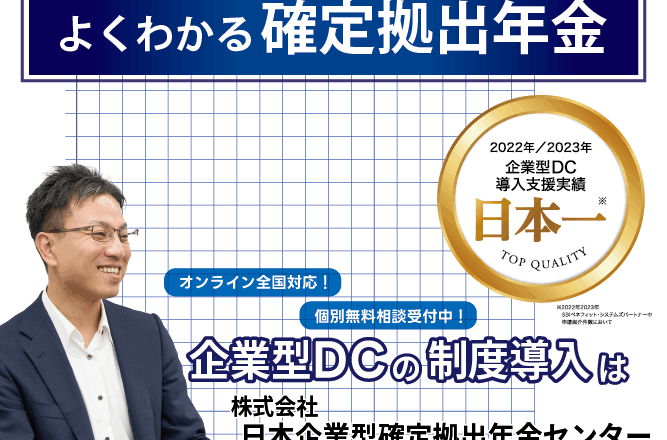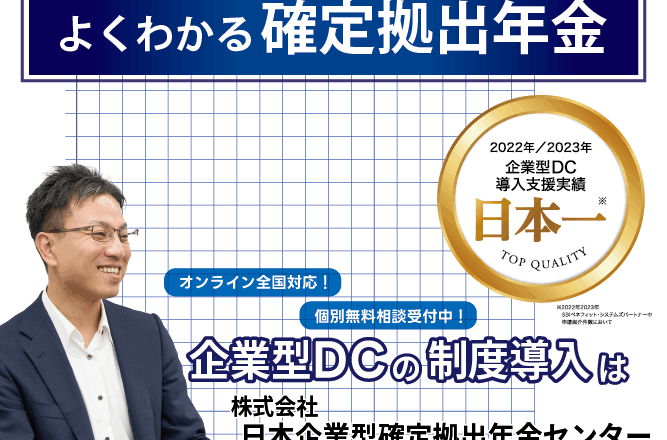
Column
コラム
コラム
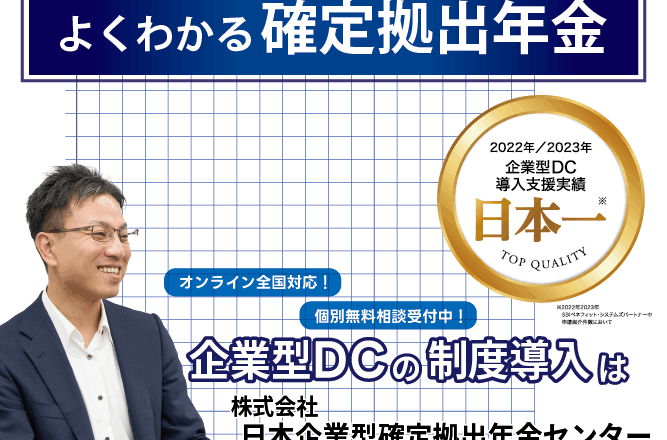
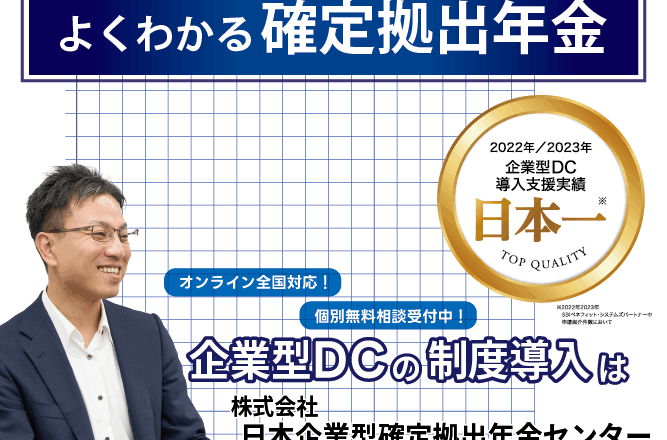
資産形成とは?初心者向けの種類別解説と企業型DC・NISA活用...
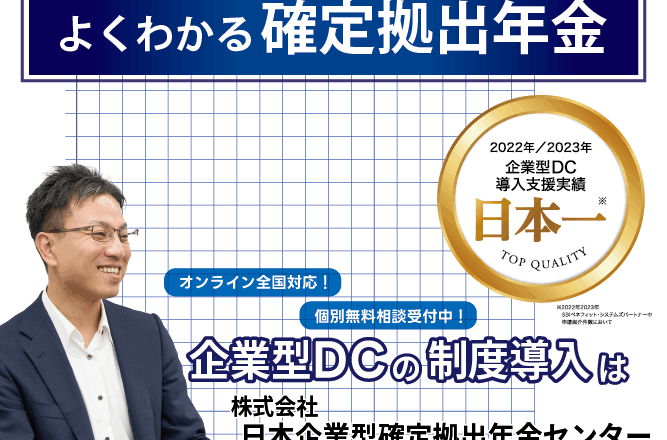
インフレとは?デフレとの違いやメカニズム、老後を守る企業型DC...
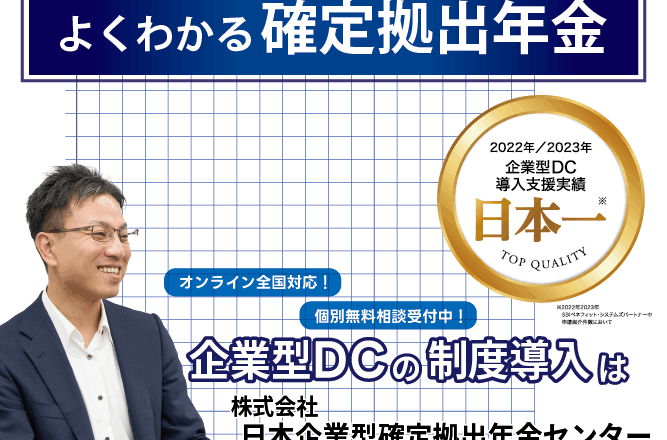
所得代替率50%の罠とは?高所得者が直面する老後の現実と企業型...
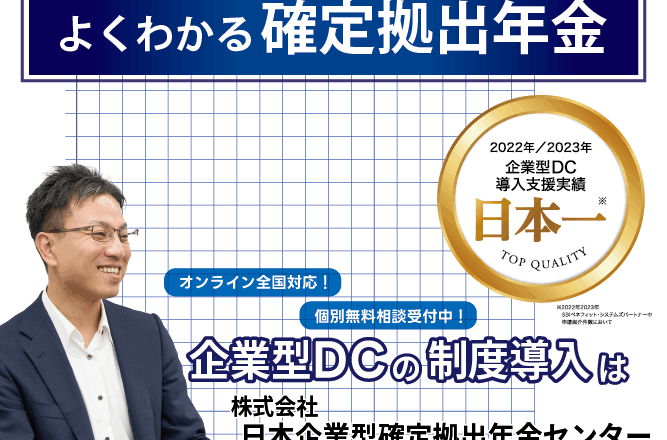
「国民年金基金は入ってはいけない」と言われる理由は?企業型DC...
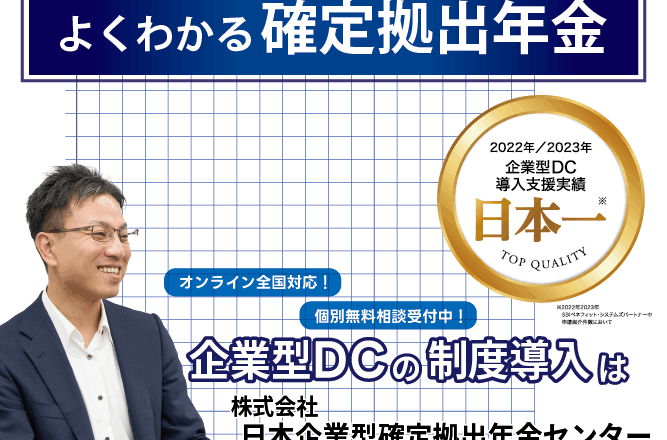
小規模企業共済等掛金控除とは?対象の種類と企業型DCとの違いを...
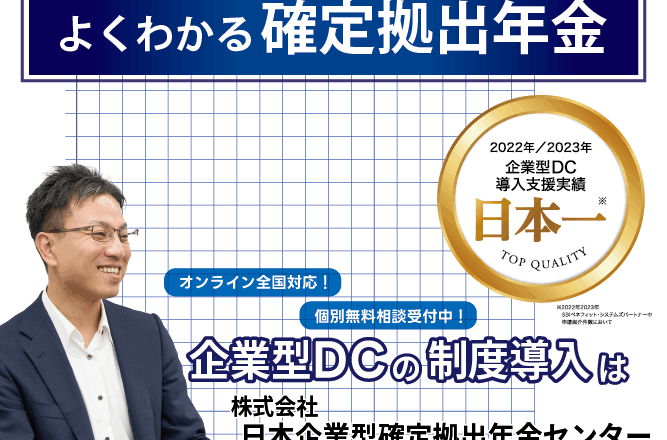
運用指図者とは?加入者との違いや切り替わるタイミング、運用のポ...
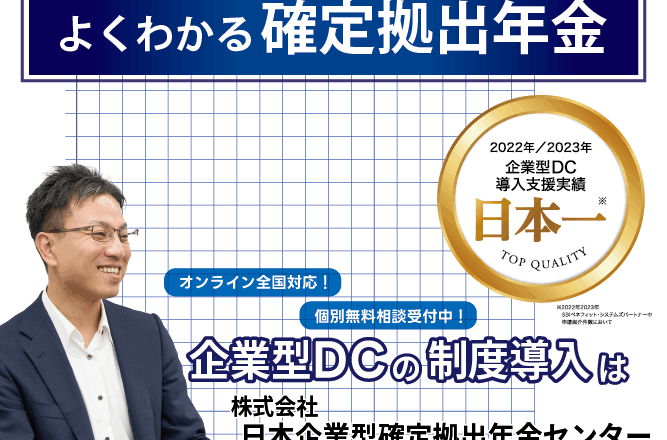
投資信託の目論見書とは|企業型DCの信託報酬を見極めるポイント
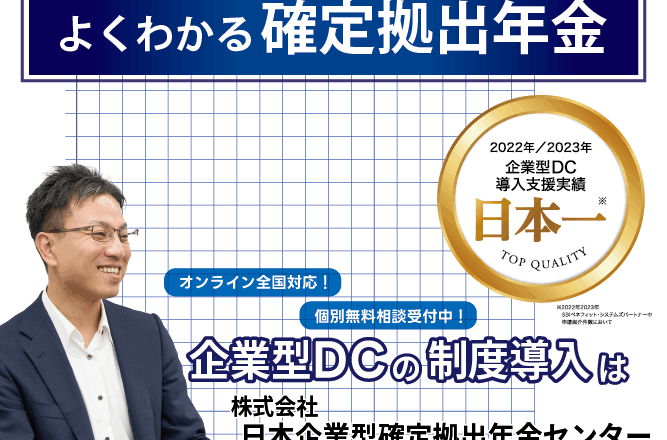
企業型確定拠出年金は毎月3,000円でも効果ある?最低掛金でも...