企業型確定拠出年金を引き出したい!退職時の脱退一時金の条件と手続き

【企業型確定拠出年金を引き出したい!退職時の脱退一時金の条件と手続き】
企業型確定拠出年金は老後の資産形成を目的とした制度のため、原則として60歳まで資産を引き出すことはできません。しかし、退職に伴い特定の条件をすべて満たした場合に限り、例外的に「脱退一時金」として現金で受け取ることが可能です。
この記事では、脱退一時金を受け取るための具体的な条件や手続きの流れ、そして条件を満たさない場合の対応方法について解説します。
動画で解説!脱退一時金ってなに?受け取れる条件とは?
脱退一時金を受け取れる条件について、動画でもわかりやすく解説しています。

1. 企業型確定拠出年金は原則60歳まで引き出せない
企業型確定拠出年金は、加入者自身が運用を行い、その成果を将来年金として受け取る私的年金制度です。
この制度の根幹は老後の所得確保を目的としているため、途中で自由に資産を引き出すことは想定されていません。

2. 例外!退職時に脱退一時金として受け取れるための条件
原則として途中引き出しができない企業型確定拠出年金ですが、退職などにより加入者資格を喪失し、かつ法令で定められたごく限定的な要件をすべて満たした場合に限り、例外として「脱退一時金」を受け取ることが認められています。
脱退一時金を請求できるのは、以下の2つのケースのいずれかに該当する場合です。

ただし、この条件は非常に限定的であり、誰もが利用できるわけではありません。
これから、脱退一時金を受け取るためにクリアすべき具体的な条件を一つずつ確認していきます。
ケース1:資産額が15,000円以下の少額である場合
退職時点での年金資産の額がごく少額(15,000円以下)であれば、比較的シンプルな要件を満たすことで脱退一時金を受け取れます。以下の条件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 詳細 |
| 【要件1】請求期間 | 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月以内であること |
| 【要件2】資産額 | 個人別管理資産額が15,000円以下であること |
| 【要件3】他のDC制度への不加入 | 企業型DCの加入者・運用指図者、またはiDeCoの加入者・運用指図者のいずれでもないこと(自動移換も完了していないこと) |
| 【要件4】過去の受給 | 過去に脱退一時金を受け取ったことがないこと |
| 【要件5】障害給付金 | 障害給付金の受給権者ではないこと |
ケース2:資産額が15,000円を超える場合(iDeCoに加入できないなど)
資産額が15,000円を超えていても、退職後にiDeCo(個人型確定拠出年金)へ加入できないなど、より厳しい以下の条件をすべて満たした場合に、例外として脱退一時金を受け取ることができます。
| 要件 | 詳細 |
| 【要件1】請求期間 | 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月以内であること |
| 【要件2】年齢 | 60歳未満であること |
| 【要件3】他のDC制度への不加入 | 企業型DCの加入者・運用指図者、またはiDeCoの加入者・運用指図者のいずれでもないこと(自動移換も完了していないこと) |
| 【要件4】iDeCo加入資格 | iDeCoに加入できない者であること(国民年金保険料免除者、一部の海外居住者などが該当) |
| 【要件5】国籍・居住地 | 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)ではないこと |
| 【要件6】通算期間または資産額 | 確定拠出年金制度に掛金を拠出した通算期間が5年以内であること、または個人別管理資産額が25万円以下であること(どちらか一方を満たせば良い) |
| 【要件7】過去の受給・障害 | 過去に脱退一時金を受け取ったことがないこと、および障害給付金の受給権者ではないこと |
※重要: 現在は法改正により、ほとんどの方がiDeCoに加入できるようになったため、「日本国内に住んでいる一般的な転職者・退職者」がケース2の条件を満たして一時金を受け取れることは、実質的にほぼありません。(受け取れるのは、次の仕事が決まっていない国民年金保険料免除者や、外国籍で帰国される方など、極めて限定的です。)
【補足】iDeCo加入者の脱退一時金について
企業型DCではなく、iDeCoに加入していた人が脱退一時金を請求できるケースも存在します。その場合は、上記の【ケース2】とほぼ同じ要件に加え、最後にiDeCoの資格を喪失してから2年以内に請求する必要があります。
いずれのケースにおいても、請求期間を過ぎてしまうと脱退一時金を受け取る権利を失います。また、手続きの開始は、以前勤めていた会社の担当部署や運営管理機関に連絡することから始まります。
3. 脱退一時金を受け取るための具体的な申請手続きと流れ
全ての条件を満たしている場合、脱退一時金の申請手続きを進めることができます。

まず、退職した会社が契約していた運営管理機関に連絡を取り、「脱退一時金裁定請求書」を入手します。 請求書に必要事項を記入し、本人確認書類などの必要書類を添えて提出します。 手続きが完了すると、指定した口座に一時金が振り込まれます。
このとき受け取る脱退一時金は、本来60歳以降に受け取るべき資産を早期に引き出すため、退職金とは異なり『一時所得』として課税されます。退職所得控除などの税制上の優遇は適用されず、所得税の課税対象となる点に注意が必要です。
4. 脱退一時金の条件を満たさない場合の2つの選択肢
年金資産が15,000円を超えるなど、脱退一時金の支給条件を満たさなかった場合、積み立てた資産を現金化することはできません。
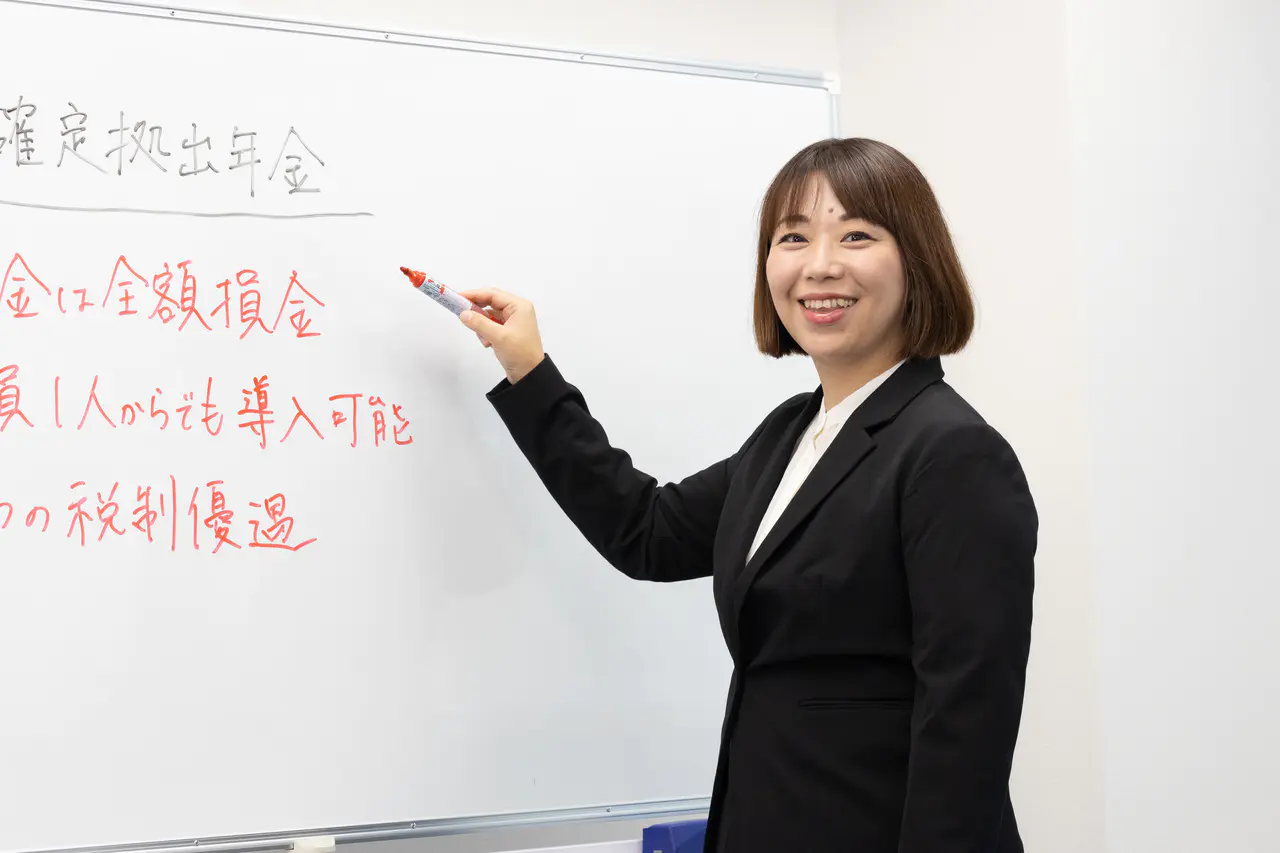
しかし、その資産がなくなるわけではなく、別の制度に引き継いで運用を続けることになります。 これを「移換」と呼びます。
退職後の状況に応じて、主に2つの移換先が考えられます。 放置するとデメリットが生じるため、退職後6ヶ月以内に必ずどちらかの手続きを行う必要があります。
選択肢1:転職先の企業型DCに資産を移換する
転職先に企業型確定拠出年金の制度がある場合、これまで積み立てた年金資産をそちらに移換するのが一般的な選択肢です。 手続きは、主に転職先の企業の担当部署を通じて行います。
必要な書類を取り寄せ、前の会社の制度から新しい会社の制度へ資産を移す旨を申し出ます。 この手続きにより、それまでの運用資産を継続して管理・運用することが可能となり、新たな会社の掛金と合算して将来の年金資産を形成していくことになります。
資産を途切れさせることなく、一元管理できる点がメリットです。
選択肢2:iDeCo(個人型確定拠出年金)に資産を移換する
転職先に企業型確定拠出年金の制度がない場合や、自営業者・公務員になる場合、あるいは専業主婦(主夫)になる場合は、iDeCo(個人型確定拠出年金)に資産を移換することになります。
この手続きは、自身でiDeCoの取り扱いがある金融機関を選び、口座開設を申し込むところから始まります。 口座開設の際に、企業型DCからの資産移換を申し出ることで、これまで積み立てた資産をiDeCo口座に移して運用を継続できます。
5. 要注意!退職後に企業型DCの手続きを放置するデメリット
退職後、企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産について、脱退一時金の請求や他の制度への移換手続きをせず、加入者資格を喪失したまま6ヶ月が経過すると、様々なデメリットが生じます。

大切な年金資産を守り、将来のために有効活用するためにも、手続きを放置することのリスクを正しく理解し、速やかに行動することが求められます。
放置した結果、資産が目減りしたり、運用機会を失ったりする可能性があります。
新たな運用ができず資産が増やせなくなる
退職後に企業型DCの手続きを放置すると、まず掛金の拠出が停止します。 新たな資金が積み立てられることはなく、掛金は0円の状態となります。
それまでのように運用商品を選んだり、配分を変更したりする「運用指図」もできなくなります。 資産は現金化された状態で留め置かれるため、市場が好調な局面であってもその恩恵を受けることができず、資産を積極的に増やす機会を完全に失ってしまいます。
将来受け取る年金額を増やすためには、継続的な拠出と運用が不可欠です。
管理手数料が継続して口座から引かれ続ける
運用が停止している状態であっても、年金資産を管理するための手数料は継続的に発生します。 企業型DCに加入中は会社が負担してくれていた手数料も、退職後は自己負担となるケースが一般的です。
新たな掛金の拠出がなく、運用によるリターンも期待できない中で、管理手数料だけが毎月資産から差し引かれ続けることになります。
長期間放置すればするほど、手数料によって大切な年金資産が徐々に目減りしていくことになり、これは大きなデメリットと言えます。
国民年金基金連合会へ自動的に移換されてしまう
退職後、移換などの手続きをしないまま6ヶ月が経過すると、積み立てた年金資産は個人の意思とは関係なく、国民年金基金連合会に自動移換されます。
自動移換された資産は、特定の個人向け年金制度の口座で管理されるわけではなく、現金化された状態で仮預かりのような状態になります。 この状態では運用が一切行われないうえ、通常よりも高い管理手数料が差し引かれ続けます。
6. 【参考】脱退一時金以外で年金を受け取れる2つのケース
企業型確定拠出年金は原則60歳からの老齢給付が基本ですが、脱退一時金の他にも、特別な事情が生じた場合に60歳未満でも給付を受けられる例外的なケースがあります。

それは、加入者が高度な障害を負った場合と、亡くなった場合です。 これらのケースでは、それぞれ「障害給付金」「死亡一時金」として、それまでに積み立てた年金資産を受け取ることが可能になります。(税金が発生する場合があります。)
高度な障害を負った場合に受け取れる「障害給付金」
加入者が75歳になるまでに、法令で定められた一定以上の障害状態になった場合、老齢給付金の受給開始年齢である60歳を待たずに「障害給付金」として年金資産を受け取ることができます。
対象となる障害の状態は、障害基礎年金の受給者や身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳(最重度または重度)、精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の交付を受けていることなどが該当します。
請求には医師の診断書など、障害の状態を証明する書類が必要となり、年金または一時金での受け取りを選択できます。
加入者が亡くなった場合に遺族が受け取れる「死亡一時金」
企業型確定拠出年金の加入者が亡くなった場合、その遺族は積み立てられていた年金資産を死亡一時金として受け取ることができます。 遺族は運営管理機関に対して死亡の事実を届け出て、死亡一時金の請求手続きを行います。
受け取ることができる遺族の範囲と順位は法律で定められており、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。
7.まとめ
企業型確定拠出年金は、原則として60歳まで引き出せない老後資金ですが、退職時に限り、ごく例外的な条件を満たせば脱退一時金として受け取れます。
その条件は、資産額が15,000円以下であることや、加入期間が5年以下であることなど非常に厳格です。

もし条件に合致しない場合は、転職先の企業型DCやiDeCoに資産を移換する手続きが必須となります。
退職後6ヶ月以内に手続きをしないと、資産が自動移換され、手数料負担が増えるなどの不利益が生じます。 自身の状況を確認し、定められた期間内に適切な手続きを完了させることが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q 退職したら、積み立てたお金はすぐに現金で受け取れますか?
A 原則として受け取れません。
企業型確定拠出年金は老後の資産形成が目的のため、60歳までは引き出せないのがルールです。
ただし、資産が15,000円以下であるなど、特定の条件を満たした場合に限り「脱退一時金」として受け取れることがあります。
Q 資産が15,000円以下なら、必ず受け取れますか?
A 必ず受け取れるわけではありません。
資産額だけでなく、他の確定拠出年金(iDeCoなど)に加入していないことや、資格喪失日の翌月から6ヶ月以内であることなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。
Q 日本国内で転職しますが、資産を現金化してリセットしたいです。可能ですか?
A ほとんどの場合、できません。
現在は法改正により多くの人がiDeCoに加入できるようになったため、日本国内に住んでいて転職・退職をする一般的なケースでは、脱退一時金の受給要件(ケース2)を満たせず、資産の「移換」手続きが必要になります。
















