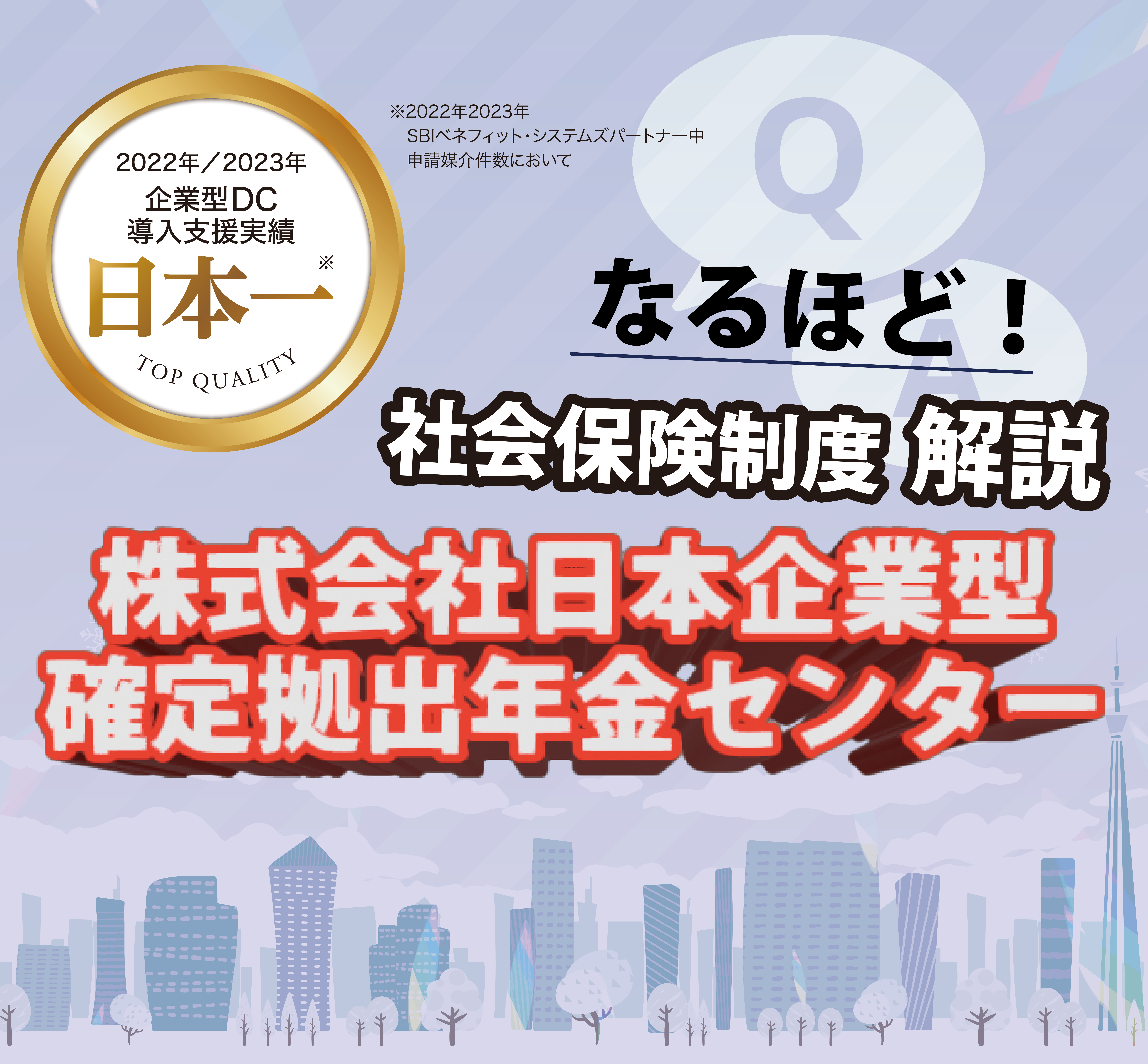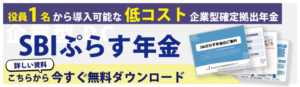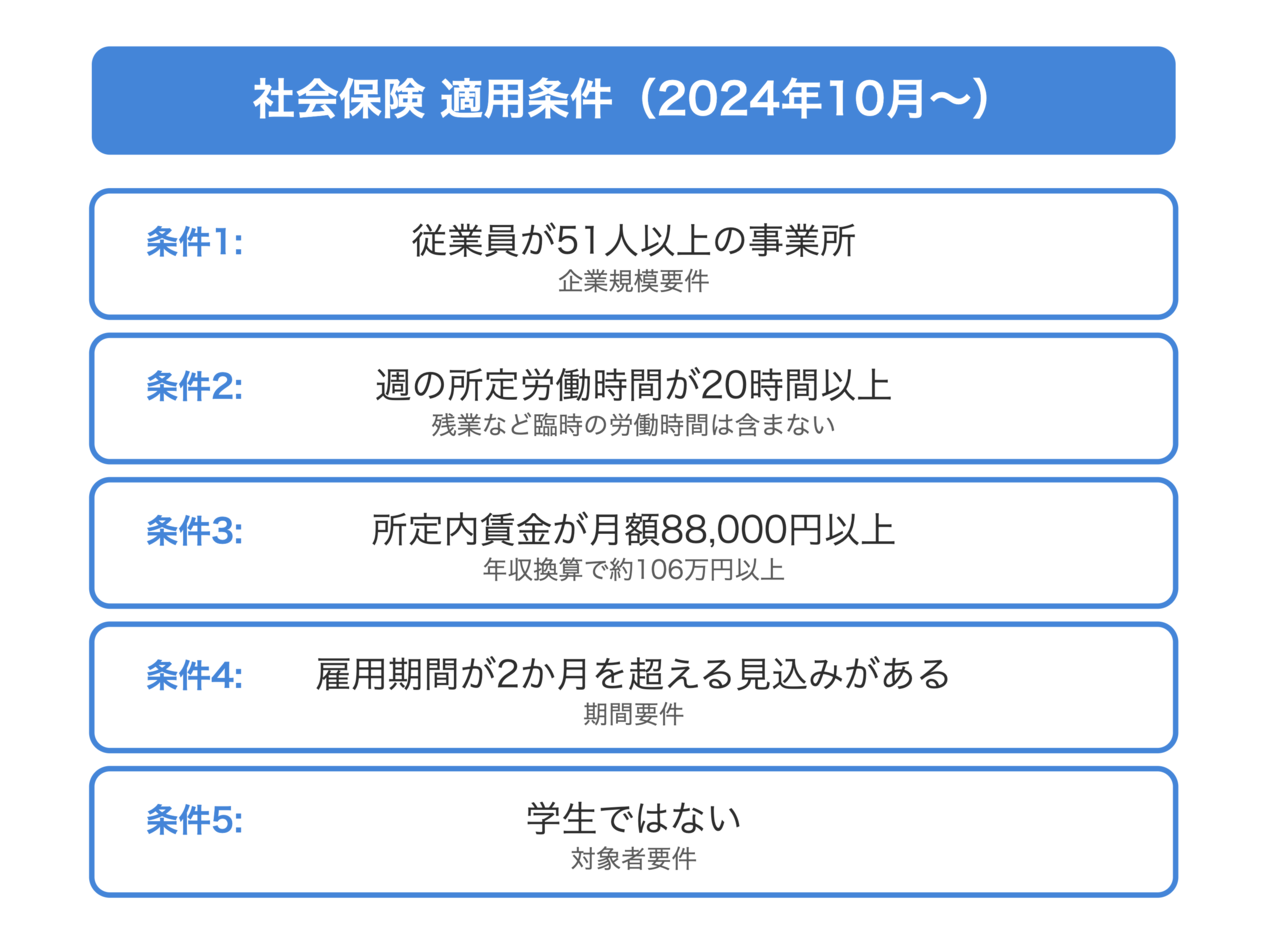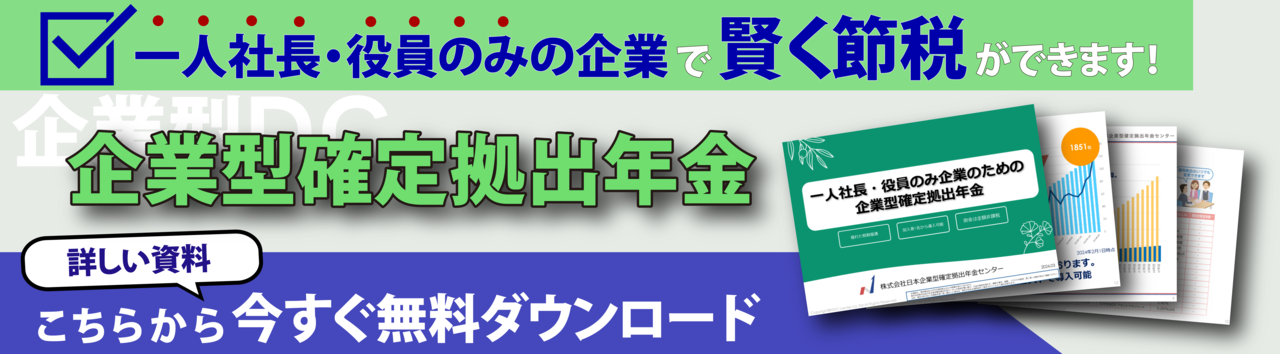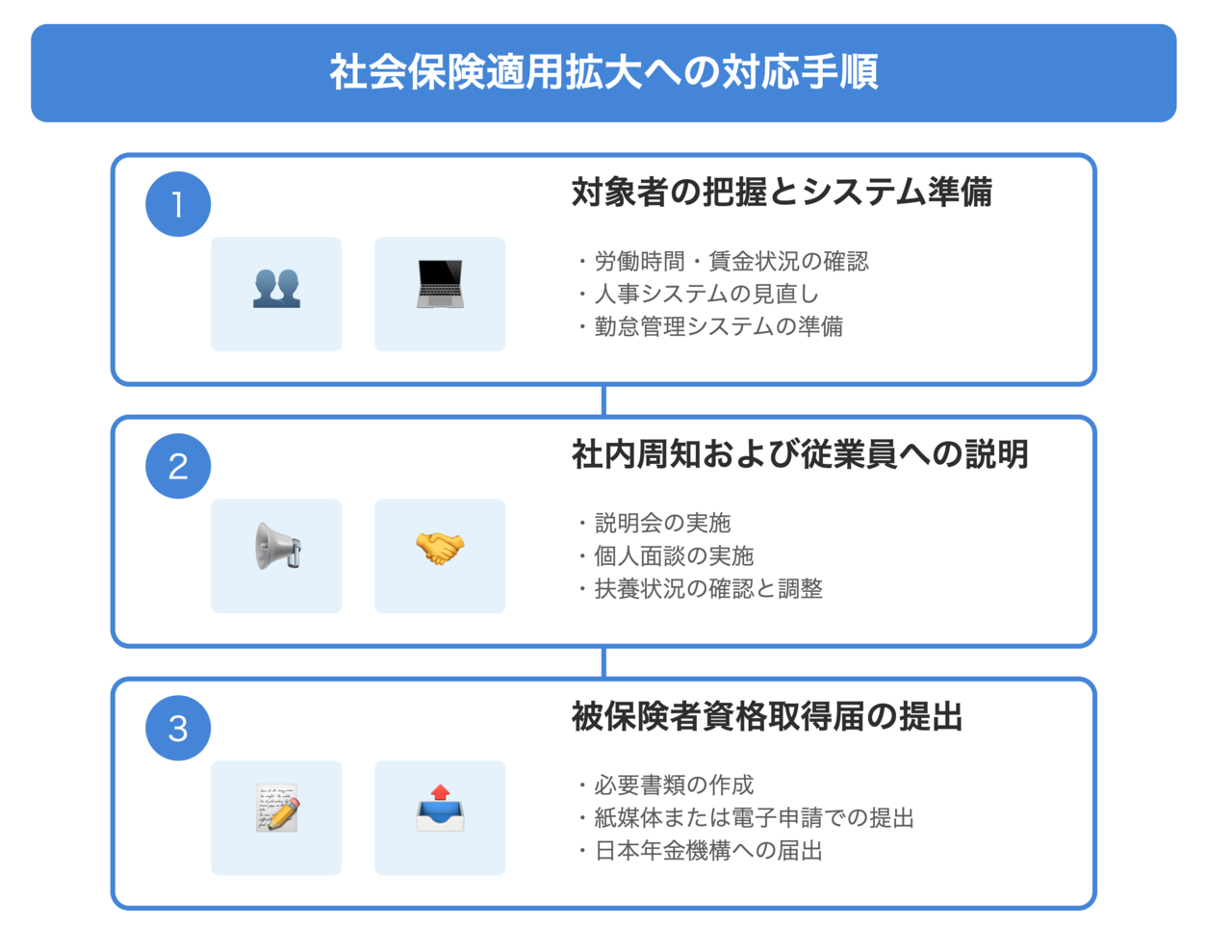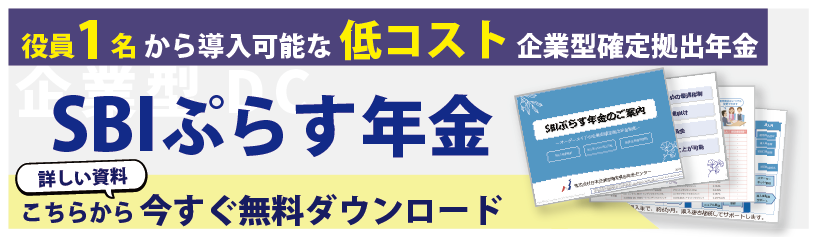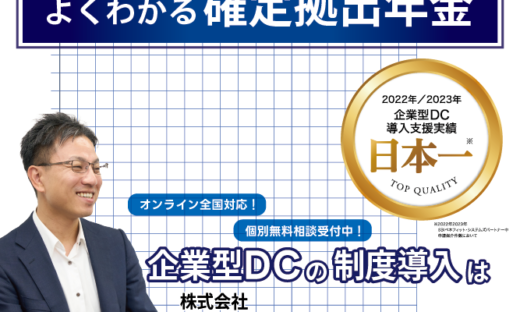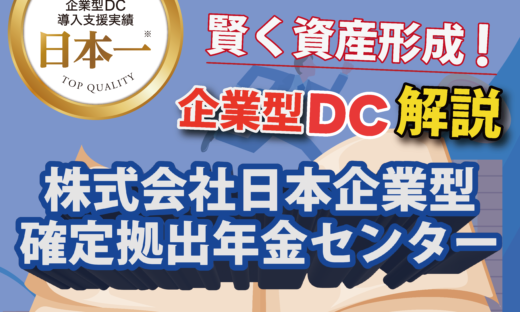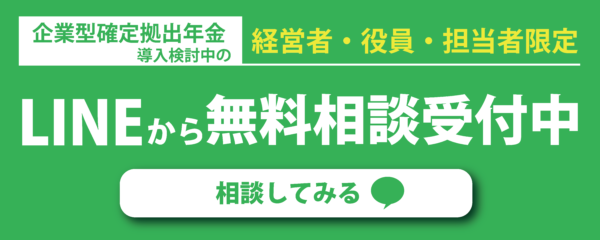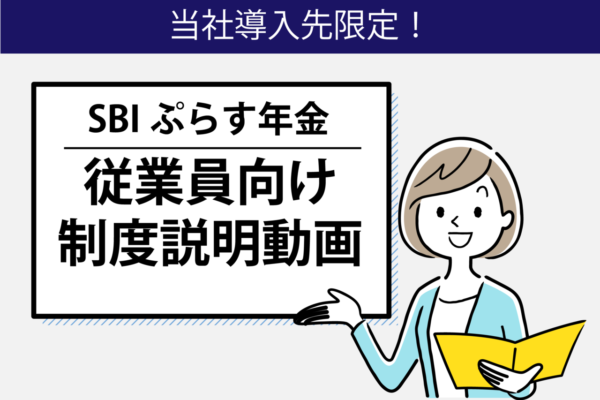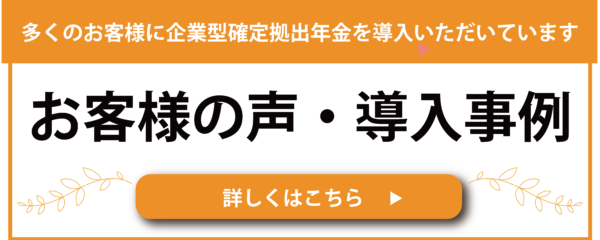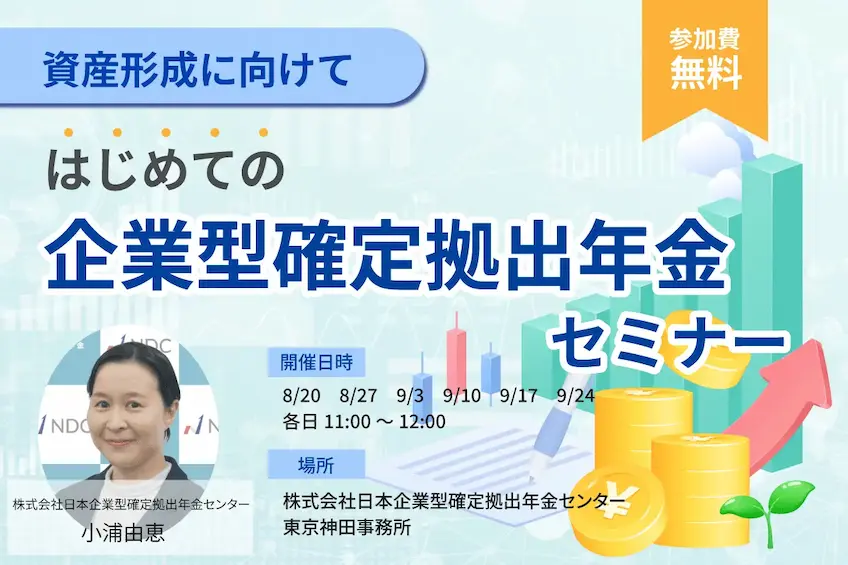Column
コラム
関連記事
コラムカテゴリー
コラム
- 投資信託の利回りはすごい?平均値や計算方法を解説 2025年6月10日
- マッチング拠出と選択制確定拠出年金(企業型DC)の制度の違いを解説 2025年3月14日
- 確定拠出年金は退職後どうすればいいの? | 放置してはいけない理由を解説! 2025年3月14日
- 企業型確定拠出年金 (DC) がひどいと言われる理由とは?メリットとデメリットを理解しよう 2025年3月14日
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金はどのように決めたらいい? | 掛金について解説 2025年3月14日
- 選択制の企業型確定拠出年金(企業型DC=401k)で年収が下がる? 従業員に丁寧に説明すべきことについて、日本企業型確定拠出年金センターが解説します。 2025年3月14日
- 役員退職金が否認された事例とは? | 「退職の事実」や「不相当に高額」の意味も解説 2025年3月14日
- 勤続年数8年の退職金は平均いくら?大企業・中小企業別に相場を紹介 2025年3月14日
- パート・有期雇用の企業型確定拠出年金(企業型DC/401k)。同一労働同一賃金と加入資格について日本企業型確定拠出年金センターの専門家が解説します。 2025年3月14日
- 選択制の企業型確定拠出年金(企業型DC=401kを導入すると、残業代はどうなる? 2025年3月14日