企業型DC・iDeCoの障害給付金とは?障害年金についても解説

企業型DC・iDeCoの障害給付金とは?障害年金についても解説
企業型DC(確定拠出年金)やiDeCoは老後資金の準備が主な目的ですが、加入者が病気やケガで障害を負った場合に備える「障害給付金」という仕組みも存在します。
一方で、国には公的制度として「障害年金」があります。 この二つの制度は、障害を持つ人々の生活を支える点で共通していますが、その性質や支給要件は異なります。
本記事では、企業型DC・iDeCoの障害給付金と障害年金それぞれの基本的な仕組み、受給額の目安、手続きの流れを解説し、両方の制度を併せて受け取れるのかという点についても明らかにします。
1. 企業型DC・iDeCoで受け取れる「障害給付金」とは?
企業型DC(企業型確定拠出年金)やiDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金を自分で運用しながら積み立て、原則60歳以降に老齢給付金として受け取る私的年金制度です。

しかし、これらの制度は老後の備えだけでなく、加入期間中に法令で定められた一定以上の障害状態になった際に、年金資産を早期に受け取ることができる「障害給付金」という保障機能も備えています。
障害給付金とは:老齢給付金とは別の特別給付
障害給付金は、確定拠出年金法に基づいており、加入者が75歳に達する前に、特定の障害状態になった場合に請求できる給付金です。老齢給付金の受給資格期間(原則10年以上)を満たしていなくても、この要件を満たせば受け取ることが可能です。
この給付は、老後の資産形成を目的とする確定拠出年金制度において、障害による生活の困難や収入の減少を補うための緊急的な所得補償として機能します。
「一定の障害状態」の具体的な要件
障害給付金の支給対象となる「一定の障害状態」は、確定拠出年金法とその関連法令により、厳格に定められています。主に公的年金制度における障害認定や、公的な手帳の交付状況に基づき判断されます。
具体的には、以下のいずれかに該当することが、一般的な支給要件となります。
公的障害年金の受給権者:
◎国民年金法・厚生年金保険法に基づく障害等級1級または2級の障害年金の受給権者であること。
特定の公的手帳等の所持者:
◎身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳(1級から3級)の交付を受けていること。
◎知的障害者福祉法に基づく療育手帳(最重度または重度)の交付を受けていること。
◎精神保健福祉法に基づく精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の交付を受けていること。
これらの要件のうちいずれか一つを満たせば請求の対象となりますが、加入している企業型DCの規約やiDeCoの運営管理機関によって、詳細な条件が異なる場合があるため、自身の制度の規約を確認することが重要です。
受け取り方法の選択肢と税制上の優遇
障害給付金の受け取り方は、一時金として一括で受け取る、または年金形式で分割して受け取るかを選択できるのが一般的です。具体的な条件や選択肢は、加入している制度の規約によって異なります。
特に重要な点として、障害給付金は税制上優遇されています。全額が非課税扱いとなるため、老齢給付金として受け取る際にかかる税金(公的年金等控除や退職所得控除)が適用されません。これは、障害による経済的な負担を軽減するという制度の趣旨を反映した措置です。

2. 国の公的制度である「障害年金」の基本を解説
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出るようになった場合に、国から支給される公的な年金制度です。
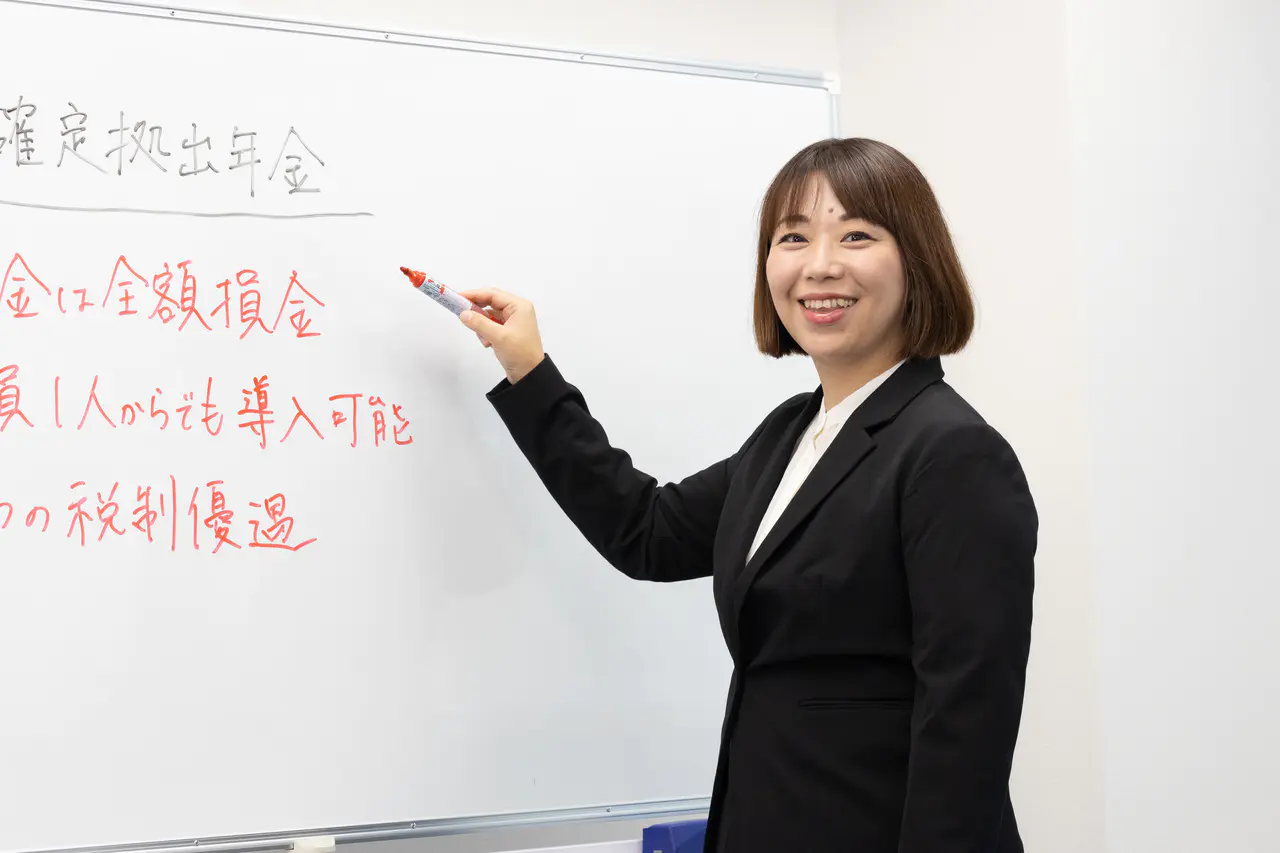
年金というと高齢者が受け取るイメージが強いですが、障害年金は現役世代を含む幅広い年齢層が対象となります。
この制度には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、どの公的年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が決まります。
障害年金とは病気やケガで生活や仕事が制限されたときに受け取れる年金
障害年金は、公的年金の被保険者が、病気やケガを原因として法令に定められた障害等級に該当した場合に支給される所得保障制度です。
この制度の目的は、障害によって働くことが困難になり収入が減少したり、日常生活に介助が必要になったりする場合の経済的な負担を和らげることにあります。 対象となる傷病は、手足の障害といった身体的なものに限りません。 うつ病や統合失調症などの精神障害、がんや糖尿病などの内部障害も含まれており、幅広い傷病が認定の対象とされています。
年金の支給を通じて、障害を抱える人々の生活の安定を図る重要な役割を担っています。
障害の程度は1級〜3級と障害手当金に区分される
障害年金の対象となる障害の程度は、国民年金法施行令および厚生年金保険法施行令に定められた障害等級表に基づいて判断され、重い方から1級、2級、3級に区分されています。
障害基礎年金は1級と2級が支給対象です。 一方、障害厚生年金は1級から3級までが対象となり、さらに3級よりも軽い障害が残った場合には、一時金として障害手当金が支給される制度もあります。

3. 障害年金と企業型DC・iDeCoの障害給付金は併給できる?
病気やケガで障害を負った場合、国の公的制度である障害年金と、私的年金制度である企業型DC・iDeCoの障害給付金の両方を受け取れるのかは、多くの人が疑問に思う点です。

結論から言うと、この二つの給付は、それぞれの支給要件を満たしていれば併給することが可能です。 なぜなら、両者は制度の根拠となる法律や運営主体、そして障害の認定基準などが全く異なる、独立した制度だからです。
ここでは、なぜ併給が可能なのかを、制度の違いから解説します。
2つの制度は根拠や運営主体が異なる
障害年金と企業型DC・iDeCoの障害給付金を併給できる最も大きな理由は、それぞれの制度の成り立ちが異なる点にあります。 障害年金は、国民年金法や厚生年金保険法といった法律に基づいて国が運営する公的年金制度であり、その実施主体は日本年金機構です。
一方で、企業型DCやiDeCoにおける障害給付金は、確定拠出年金法を根拠とする私的年金制度の一環です。 その運営は、各企業が設立した年金規約や、個人が加入する金融機関(運営管理機関)のルールに基づいて行われます。
このように、公的制度と私的制度という根本的な違いがあるため、互いの給付が影響し合うことはありません。
支給条件や障害の認定基準にも違いがある
両制度は、支給の条件や障害状態の認定基準においても違いがあります。 障害年金の受給は、初診日や保険料納付の要件を満たした上で、日本年金機構が医師の診断書等に基づき、法令で定められた障害等級に該当するかを独自に審査・認定します。
これに対し、企業型DCやiDeCoの障害給付金は、多くの場合、障害年金(1級または2級)の受給権者であることや、特定の等級の身体障害者手帳等の交付を受けていることを支給の条件としています。
つまり、障害給付金は国の制度による障害認定の結果を利用する形をとることが多いものの、給付を決定するのはあくまで加入している企業や金融機関であり、認定の主体そのものが異なります。
それぞれの要件を満たせば両方受け取ることも可能
障害年金と企業型DC・iDeCoの障害給付金は、それぞれが独立した制度であるため、一方の給付を受けても、もう一方の給付が調整されたり停止されたりすることはありません。
したがって、まず国の制度である障害年金の支給要件を満たして受給が決定し、その上で、加入している企業型DCやiDeCoの規約に定められた障害給付金の支給要件(例:障害年金1級または2級を受給していること)も満たす場合には、両方の給付を同時に受け取ることが可能です。

4. 企業型DC・iDeCoの障害給付金を受け取るときの注意点
企業型DCやiDeCoの障害給付金は、一度請求して受給が決定すると、その時点で積み立てた年金資産の全額、または選択した分割形式での支給が完了し、制度上の権利は基本的に消滅します。

そのため、公的年金とは異なり、受給後の定期的な更新や等級変更手続きといった概念は適用されません。
ここでは、障害給付金を請求・受給する際に知っておくべき重要なポイントを解説します。
障害給付金請求後の企業型DC・iDeCoの加入資格
障害給付金を受け取ると、原則として、その時点で企業型DCまたはiDeCoの加入者資格を喪失し、制度から脱退することになります。
◎企業型DCの場合:
規約に基づき年金資産の全額(または一部)を受け取ると、その企業型DCの加入者資格は終了しますが、規約によっては障害給付金を受け取っても、引き続き加入者資格を継続できる場合があります。
◎iDeCoの場合:
障害給付金を受け取ると、iDeCoの加入者資格を喪失し、掛金の拠出はできなくなります。
将来的に障害の状態が回復したとしても、原則として一度障害給付金を受け取った制度に再度加入したり、掛金を拠出したりすることはできません(ただし、老齢給付金の受給資格期間を満たしていない状態で一部の資産のみを受け取った場合の扱いは、制度規約によります)。
請求前には、必ずご加入の企業型DCまたはiDeCoの運営管理機関に資格の継続について確認してください。
一時金で受け取った場合の「非課税」のメリット
障害給付金を一時金として一括で受け取った場合、その全額が所得税・住民税において非課税扱いとなります。
◎税制上の優遇:老齢給付金(一時金として受け取る場合)は「退職所得」として課税対象になりますが、障害給付金は障害による経済的な困難を補うための給付であるため、所得として計算されず、税金がかかりません。
この非課税のメリットは非常に大きく、受け取った資産をそのまま生活費や医療費などに充てることができます。
しかし、障害給付金の請求は、企業型DC・iDeCoの「脱退」を意味します。資産形成を続けることができなくなるため、請求する際は、ご自身の経済状況や公的年金(障害年金)の受給状況などを総合的に考慮し、慎重に判断することが大切です。
国民年金保険料の支払いが全額免除される
障害基礎年金、または障害等級1級・2級の障害厚生年金を受給している方は、国民年金保険料の支払いが全額免除される「法定免除」の対象となります。 この免除を受けるには、市区町村の役所の国民年金担当窓口への届出が必要です。
法定免除を受けた期間は、保険料を納付したものとして扱われますが、将来受け取る老齢基礎年金の計算上は、全額納付した場合の2分の1として反映されます。

5. まとめ
企業型DC・iDeCoの障害給付金は、老後の資産形成を目的とする確定拠出年金制度に備わる、万が一の事態に対応するための重要な保障機能です。

















