薬剤師の退職金相場はどのくらい?10年・20年・30年勤めたときの平均金額や相場を紹介

薬剤師の退職金相場はどのくらい?10年・20年・30年勤めたときの平均金額や相場を紹介
薬剤師に支給される退職金は、勤務先や定められている就業規則によって異なります。主な勤務先として病院・調剤薬局・ドラッグストアなどが考えられ、詳細な金額は勤務年数や退職理由などを加味して計算します。
公務員としての身分を有する場合や大手企業で勤務する場合は、退職金制度が整備されているケースがほとんどでしょう。一方で、小規模な調剤薬局やドラッグストアで勤務する場合、退職金がないか、あっても少額になりやすい傾向です。
今回は、薬剤師の退職金相場について解説します。また、勤務先ごとの相場も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 退職金の基本的な仕組みと代表的な制度
退職金は、従業員が企業での勤務を終えて、退職する際に支給される一時金です。これまでの貢献に対する感謝や、給与の前払いの一環として位置づけられています。

退職後の生活を経済的に支える原資となるため、退職金制度が整備されている職場であれば、安心して働けるでしょう。
なお、退職金制度と一口に言っても、さまざまな制度があります。代表的な退職金制度をまとめると、以下のとおりです。
| 退職一時金制度 | 労働協約・就業規則・退職金規程などの規定に準じて、退職金を一括で受け取る制度 |
| 企業型確定拠出年金(企業型DC) | 企業が掛金を積み立て、従業員が自身の責任で運用する制度。受け取れる退職金(年金)は運用成績に応じて変わる |
| 確定給付企業年金制度(DB) | 企業が掛金を積み立て、予定利率に基づいて受け取れる退職金(年金)が決まる |
| 中小企業退職金共済制度 | 中小企業を対象とした国が運営する退職金制度。受け取れる退職金は加入月数に応じて変わる |
なお、退職金制度は必ず設けなければならないわけではありません。勤務先によっては、そもそも退職金制度がなく、この場合は退職後の生活資金を従業員が自身で用意する必要があります。
大規模な医療機関や大手ドラッグストアなどでは退職金制度が整備されている一方で、中小規模の薬局やクリニックなどでは、退職金を導入していない場合も少なくありません。
そのため、事前に勤務先の就業規則を確認し、退職金に関連する条件を把握しておくことが大切です。
2. 薬剤師が受け取れる退職金の平均相場
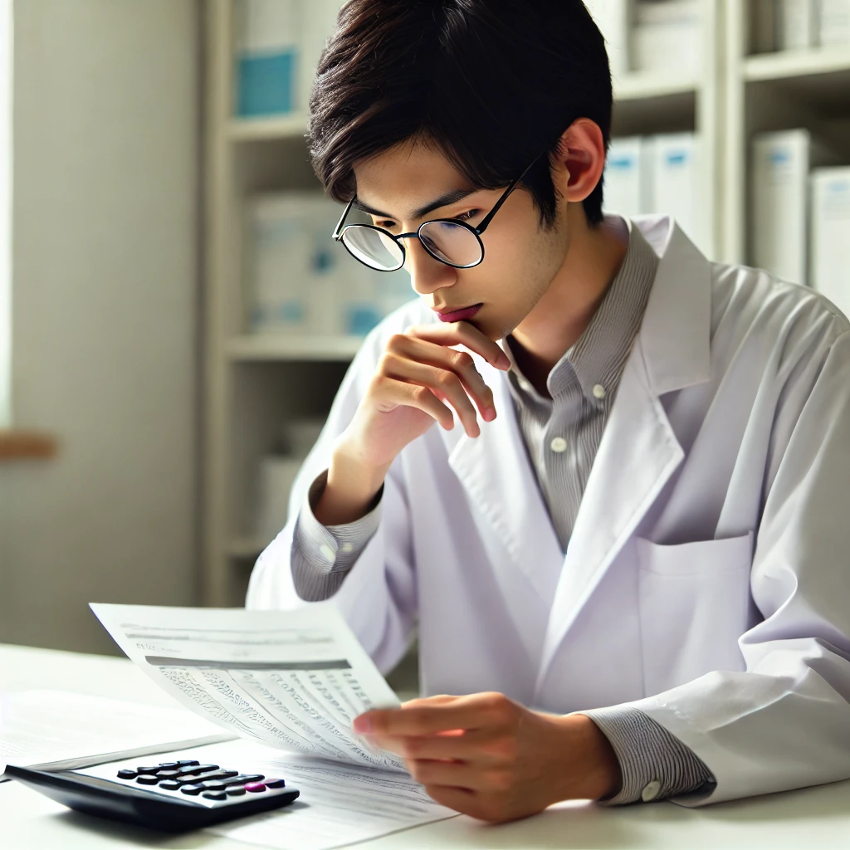
薬剤師の退職金は、勤務先によって大きく変動します。公務員として働く場合や調剤薬局・ドラッグストアで働く場合など、ケースごとに退職金の相場を見ていきましょう。
①公務員として働く場合(国公立病院など)
国公立の病院や保健所などに勤務する正職員の薬剤師は、公務員としての身分を有します。公務員の場合は、省庁や自治体ごとに定められている退職金規程に基づいて、退職金を計算します。
公務員の場合、勤続年数・退職理由・退職時の給与に基づいて計算するケースが一般的です。「勤続年数×退職理由に基づく係数×退職時の給与」で計算するため、勤続年数が長くなるほど、退職時の給与が高いほど退職金の額が増加する仕組みです。
例えば、30年間勤務して退職時の給与が40万円の場合、退職金が1,200万円になります(退職理由の係数を1とした場合)。このように、公務員は退職時の金銭的な待遇が充実しているため、安定した老後の生活設計を立てやすいでしょう。
②調剤薬局やドラッグストアで働く場合
調剤薬局やドラッグストアで働く薬剤師の退職金額は、企業規模によって異なります。上場しているような大規模な企業であれば、手厚い退職金制度が用意されていると考えられます。
勤続年数が30年以上になれば、役職や給与次第では1,000万円以上の退職金を受け取れることもあるでしょう。
一方で、中小規模の調剤薬局やドラッグストアの場合、退職金制度が整備されていないケースもあり得ます。
なお、東京都産業労働局の「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」では、すべての産業を対象としたモデル退職金が以下のように示されています。
【高校卒】
| 勤続年数 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
| 10年 | 98.5万円 | 126.4万円 |
| 15年 | 190.3万円 | 237.3万円 |
| 20年 | 288.1万円 | 342.8万円 |
| 25年 | 434.2万円 | 510.0万円 |
| 30年 | 575.7万円 | 657.0万円 |
【高専・短大卒】
| 勤続年数 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
| 10年 | 102.1万円 | 152.8万円 |
| 15年 | 185.6万円 | 227.0万円 |
| 20年 | 303.5万円 | 357.8万円 |
| 25年 | 437.3万円 | 509.9万円 |
| 30年 | 582.2万円 | 663.5万円 |
【大学卒】
| 勤続年数 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
| 10年 | 112.5万円 | 144.8万円 |
| 15年 | 209.3万円 | 255.9万円 |
| 20年 | 348.6万円 | 408.1万円 |
| 25年 | 507.3万円 | 615.6万円 |
| 30年 | 750.7万円 | 776.2万円 |
全産業を対象としているため、あくまでも目安程度に留めておくとよいでしょう。「ざっくり自分の場合はこの程度だろう」というイメージをつかむ際に、参考にしてみてください。
③民間の病院や医療施設で働く場合
民間の病院や医療施設に勤務する薬剤師の退職金は、勤務先の病院や施設の規模・種類・給与規程などによって変動します。民間の医療機関や医療施設では退職金の水準に幅があり、勤続年数が30年とすると、800万円から1,200万円程度が一般的な相場となるでしょう。
なお、やや情報は古いですが「2015年版 病院職種別モデル退職金実態資料」によると、病院に勤務している従業員のモデル退職金は以下のとおりです。
| 勤続年数 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
| 1年 | 11.4万円 | 24万円 |
| 3年 | 33.7万円 | 54.5万円 |
| 5年 | 64.7万円 | 98.6万円 |
| 10年 | 174万円 | 244.1万円 |
| 15年 | 353.8万円 | 463.8万円 |
| 20年 | 613.7万円 | 719.6万円 |
| 25年 | 902.9万円 | 1006.3万円 |
| 30年 | 1163.3万円 | 1276.6万円 |
| 35年 | 1388万円 | 1541.1万円 |
| 40年 | 1364.3万円 | 1477.2万円 |

3. 薬剤師の退職金の算定方法について

退職金の算定方法は企業によって異なるため、勤務先ごとの具体的な規程を事前に確認しておくことが重要です。一般的には勤続年数や基本給を基に算出しますが、勤務先によっては役職・職務内容・退職理由などを反映することもあります。
また、薬剤師の専門性や資格を考慮して、独自の給付基準を設けている場合があります。以下で、薬剤師の退職金を算定する代表的な方法を見ていきましょう。
①勤続年数や基本給の影響
多くの場合、退職金の算定では勤続年数や基本給が用いられます。勤続年数に関係なく、一律で退職金を支給する例外的なケースはあるものの、短期間の勤続よりも長く勤続することで退職金の金額は大きくなるのが一般的です。
基本給をベースに退職金を計算する場合は、退職時における基本給が高いほど、受け取れる退職金額は増加します。
また、退職時の役職を退職金に反映させる仕組みを設けているケースもあります。役職が高いほど重い責任を負って重要な業務を果たしていたと考えられるため、功労や貢献に報いるためにも、役職に応じて加算を行うのです。
②退職理由による影響
退職理由も退職金に影響を与える要素です。
一般的に、自己都合退職よりも会社都合退職や定年退職のほうが退職金は高額になります。公務員の場合は離職理由ごとに係数が決められており、自己都合退職よりも会社都合退職や定年退職のほうが、係数は高く設定されています。
具体的には、定年退職や人員整理による解雇、早期退職に応じた退職などは会社都合退職です。これらの理由で退職する場合、多くの退職金が支給される傾向にあります。
企業によっては、「特別貢献者」のように特定の条件に該当する場合や、在籍した部署によって支給額を上乗せすることもあり得ます。そのため、自分の退職理由や状況がどの基準に該当するか、事前に就業規則を確認することが重要です。
③退職一時金を計算する方法の種類
退職一時金でも、以下のように複数の計算方法があります。
| 基本給連動型 | 勤続年数・退職時の基本給・退職理由によって退職金を算出する方法 |
| 定額制 | 勤務年数ごとに定められた支給額に基づき退職金を決定する方法 |
| ポイント制 | 在職中に付与されたポイントに基づいて退職金を算出する方法 |
「基本給連動型」と「定額制」の場合は、勤続年数と退職時の基本給次第で退職金が決まる、というイメージです。
しかし、昨今は在職中の成果や貢献を退職金に反映させるために、ポイント制を導入する企業が増えています。役職や仕事内容などをポイント化する仕組みを独自に設定できるため、柔軟な制度設計が可能です。
4. 薬剤師の退職金を確認する手順
薬剤師が自身の受け取れる退職金を確認するときは、就業規則や退職金規定を見ましょう。

ほかにも、労務担当者へ確認したり退職予定者へ直接聞いたりする方法もあります。
①就業規則や労務担当者への確認
就業規則は、労働条件や従業員が守るべきルールについて、具体的に記載された文書です。退職金については「退職金規程」という項目で、支給額や受給条件など詳細に記載されています。
就業規則や退職金規程はいわゆるルールブックにあたるため、細部に至るまでしっかりと確認すれば、自分の退職金を確認できるはずです。また、就業規則には「懲戒解雇者には退職金を支給しない」のような例外事項が設けられているケースもあるため、見落としがないよう注意深く読みましょう。
就業規則や退職金規程の文言だけでは理解が難しい場合は、労務担当者に直接相談する方法があります。労務担当者は自社の退職金制度に精通しているため、自分の事例に落とし込んで、詳細に金額を計算してくれるでしょう。
②制度ごとに確認方法は異なる
勤務先によって、導入している退職金制度は異なります。退職一時金だけでなく企業型確定拠出年金や確定給付企業年金のような企業年金制度を導入しているケースでは、定期通知やインターネット上のマイページで運用状況を確認する方法があります。
企業年金は入社と同時に加入するのが一般的で、本人に加入している自覚がないケースも少なくありません。「加入者口座番号」や「インターネットパスワード」などが伝えられている可能性があるため、ログインしてみるとよいでしょう。
5. 退職金を受け取る前に考えておくべきこと
退職金は、まとまった金額を受け取れる数少ない機会です。退職後の生活を支える貴重なお金となるため、取り扱いについて事前に十分な計画を立てることが重要です。

特に、定年退職に伴って退職金を受け取る場合は、老後資産の一部となります。一括で受け取る方法や年金形式で分割受給する方法があるため、自分のライフステージや生活状況などによって、最適な受け取り方法を考えましょう。
| 受け取り方法 | 特徴 | 向いている人 |
| 一時金 | まとまった金額を一度に受け取る |
|
| 年金 | 年金形式で定期的に受け取る |
|
退職金を一時金と年金のどちらで受け取るかを決める際には、今後のライフプランを考える必要があります。
退職時における支出計画や生活水準、医療費などを考え、定期的な収入が必要かどうか検討しましょう。一般的に、高齢になると医療や介護サービスを受ける機会が増えるため、急な医療費用や介護費用が発生する可能性も考慮に入れる必要があります。
また、「いつまで働く予定なのか」「公的年金を繰下げ受給する予定はあるのか」も加味しましょう。公的年金を繰り下げるのであれば、その間の生活費を勤労収入や退職金でまかなう必要があります。

健康状態や生活設計など、個々の状況に応じて一時金と年金のメリット・デメリットを比較することが大切です。最適な選択は一概にはいえないため、さまざまなケースを想定して「自分にとってベストは受け取り方法」を考えてみてください。
6. 企業型確定拠出年金は負担を抑えて退職金制度を用意できる
退職金制度にはいくつか種類がありますが、企業型確定拠出年金は効率よく従業員の退職金を用意できる制度として注目されています。

企業型確定拠出年金では退職給付債務が発生しないため、退職金制度がない中小規模にとって導入しやすい制度です。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために用意した年金口座に掛金を拠出し、従業員が自身で資産運用を行う仕組みです。自社の責任で、積み立てたり運用したりする必要がありません。
従業員は、運用している年金資産を持ち運べます。退職時や転職時に、企業が退職一時金を支払う必要はありません。
また、「選択制企業型確定拠出年金」では、加入を希望する従業員が自分の給与から掛金を拠出します。制度そのものの自由度が高く、従業員が各自のライフプランに合わせて柔軟に活用できるメリットがあります。

7. まとめ:薬剤師の退職金を用意して優秀なスタッフを確保しよう
薬剤師が受け取れる退職金額は、働く環境や仕事内容、キャリアなどによって異なります。勤務先の規模だけでなく、勤続年数や退職時の給与、退職理由などが金額に反映される点を押さえておきましょう。

また、薬剤師の中には国公立病院や自治体の保健所に勤務する公務員の方がいる一方で、民間企業に勤務する方もいます。中小企業に勤務する場合は、そもそも退職金制度がない可能性があります。
スタッフのために退職金制度を用意したいと考えている医療機関や薬局の事業主の方は、企業型確定拠出年金の導入がおすすめです。企業負担の財務的な負担が軽いうえに、従業員自身が非課税で運用しながら、効率よく退職金制度を用意できます。
日本企業型確定拠出年金センターでは、導入時と導入後の支援を行っています。各企業に合った最適な制度を提案し、また煩雑な事務もサポートいたしますので、ご安心ください。

弊社は導入支援実績2年連続日本一となっており、業界最安水準の事務取次手数料、スムーズな対応を強みとしています。2025年3月まで、導入費用を5万円OFFになるキャンペーン実施しているため、お得な機会をぜひご利用ください。




















