50代からの資産形成は企業型DC・iDeCo・NISAどれがいい?わかりやすく解説します

50代からの資産形成は企業型DC・iDeCo・NISAどれがいい?わかりやすく解説します
50代は子育てが一段落し、定年を意識し始めるなど、ライフステージが大きく変化する時期です。老後資金や将来のライフイベントへの備えとして、本格的に資産形成を考え始める方も多いのではないでしょうか。
本記事では、50代の方が資産形成を始めるにあたり、代表的な制度である企業型DC・iDeCo・NISAについて、それぞれの特徴や違い、ご自身の目的に合った選び方をわかりやすく解説します。
動画で解説:50代からの企業型確定拠出年金|おすすめ配分で賢く資産形成
50代からの老後資産形成の1つとして、企業型確定拠出年金がおすすめな理由を解説します。

1. 【結論】50代の資産形成は目的別に確定拠出年金とNISAを使い分けるのがおすすめ
50代からの資産形成において、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)とNISAのどちらか一方を選ぶのではなく、それぞれの制度の特性を理解し、目的別に使い分けることが最適な選択です。

「老後資金を確実に貯めたい」「税金の負担を軽減したい」という目的であれば企業型DCやiDeCo(確定拠出年金)が特に有効です。また、近い将来の出費(教育費、リフォーム費用など)に充てたい」といった流動性を重視するならNISAが適しています。
両方の制度を併用することで、高い節税メリットと資金の柔軟性を両立させることが可能です。

2. 50代が知っておきたい確定拠出年金とNISAの制度概要
50代から資産形成を始める上で、まずは各制度の基本的な仕組みを正確に理解することが重要です。
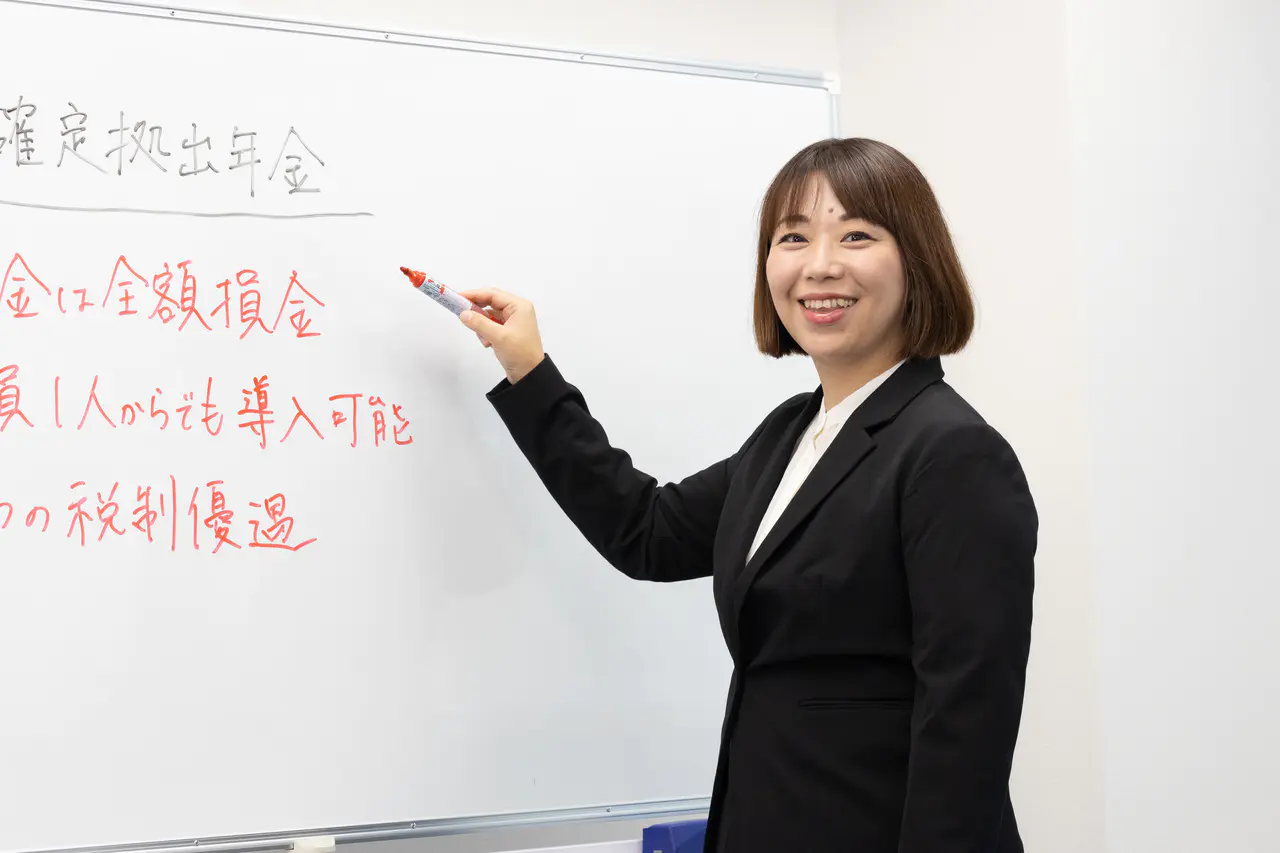
企業型DC、iDeCo、NISAは、いずれも税制上の優遇措置を受けながら資産形成ができる国の制度ですが、その特徴は大きく異なります。
企業型DC(企業型確定拠出年金)は税制優遇と企業負担の手数料が大きなメリット
企業型DC(企業型確定拠出年金)は、役員・従業員自身が運用商品を選んで資産を形成する私的年金制度です。
選択制DC(選択制確定拠出年金)では、給与の一部を「生涯設計手当」などの形で受け取るか、企業型DCの事業主掛金として拠出するかを従業員が選択できる仕組みです。役員は、全額損金で積み立て可能です。また、従業員については掛金に回した分は給与算定対象外となるため、所得税・住民税の課税対象外となり、実質的な手取りが大きくなります。
また、口座管理手数料は原則として、福利厚生費として会社が負担します。(在職中に限ります。)
企業型DCの一つであるマッチング拠出は、事業主掛金に加えて従業員が掛金を上乗せするもので、上乗せした掛金についてはiDeCoと同様に全額所得控除の節税効果を得られます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は全額所得控除の節税メリットが大きい
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、個人が任意で加入し、自分で掛金を拠出して運用する私的年金制度です。最大の特長は、掛金の全額が所得控除の対象になることで、所得税や住民税の負担を軽減しながら将来の資産を準備できます。
ただし、企業型DCと違い、口座管理手数料などが個人負担であることに注意が必要です。
NISAは運用益が非課税になる少額投資制度
NISAは、毎年の非課税投資枠の範囲内で購入した金融商品から得られる利益(配当金・分配金・譲渡益)が非課税になる制度です。2024年から始まった新しいNISAでは、非課税で保有できる期間が無期限化され、年間の投資上限額も拡大しました。
確定拠出年金とは異なり、積み立てた資産をいつでも自由に売却して引き出せる流動性の高さが特長です。そのため、近い将来の住宅リフォーム費用や子どもの結婚資金など、多様なライフイベントに備えるための資産形成に適しています。
3. 確定拠出年金とNISAの重要な違いを5つのポイントで比較
50代から資産形成を始めるにあたっては、運用できる期間が限られるため、よりご自身のライフプランに合った制度を選ぶことが重要です。

| 比較ポイント | 企業型DC | iDeCo | NISA |
| 資金の流動性 | 原則60歳まで引き出し不可 | 原則60歳まで引き出し不可 | いつでも引き出し可能 |
| 掛金拠出時の税制優遇 | 課税対象外 | 全額所得控除 | なし |
| 口座管理手数料 | 企業負担(福利厚生費) | 個人負担 | ほとんどの金融機関で無料 |
| 加入年齢の上限 | 70歳 | 65歳未満(国民年金加入が条件) | なし |
| 受け取り時の税制 | 一時金:退職所得控除 分割:公的年金等控除 |
一時金:退職所得控除 分割:公的年金等控除 |
非課税 |
| 金融商品の種類 | 運営管理機関が選定したラインナップ | 運営管理機関が選定したラインナップ | 幅広い商品から自由に選択可能 |
①加入年齢と受取開始年齢の制限
確定拠出年金は、老後資金の確保を目的としているため、加入年齢や受取開始年齢に制限があります。
1. 企業型DC:加入可能年齢は70歳です。
2.iDeCo:加入可能年齢は2022年5月から65歳未満まで延長されました(国民年金に加入していることが条件)。50歳以降に加入する場合、通算加入者等期間が10年に満たないと、受給開始年齢が61歳から65歳の間で段階的に引き上げられる点に注意が必要です。
3.NISA:加入年齢の上限はなく、成人であれば誰でも始めることが可能です。また、受取開始年齢にも制限はなく、いつでも好きなタイミングで資産を売却し、現金化できます。
確定拠出年金は、老齢給付の受給権を満たしていれば60歳以降は受給開始時期を選択できます。
②途中で資金を引き出せるかどうかの流動性
資金の流動性は、両制度の最も大きな違いの一つです。
・確定拠出年金(企業型DC・iDeCo):老後資金の確保を目的としているため、原則として60歳になるまで積み立てた資産を引き出すことはできません。計画的に老後資金を準備するメリットがある一方で、急な出費には対応できません。
・NISA:いつでも保有している金融商品を売却して現金化できます。子どもの教育費や住宅のリフォームなど、老後資金以外の突発的な資金ニーズにも柔軟に対応できる高い流動性が魅力です。
③税金の優遇措置から見た節税効果
税制優遇の面では、確定拠出年金がより手厚い仕組みとなっています。
| 制度 | 掛金拠出時 | 運用時 | 受取時 |
| 企業型DC | 課税対象外 | 非課税 | 退職所得控除/公的年金等控除 |
| iDeCo | 全額所得控除 | 非課税 | 退職所得控除/公的年金等控除 |
| NISA | なし | 非課税 | 非課税 |
特に50代は所得が高い傾向にあるため、課税対象外や所得控除による毎年の税負担の軽減効果は非常に魅力的です。
④選べる金融商品の種類の幅広さ
NISAは、個別株式、投資信託、ETF(上場投資信託)など、幅広い選択肢から自由に選んで投資することが可能です。
確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)は、運営管理機関(金融機関)があらかじめ選定した、数十種類程度の金融商品ラインナップの中から選ぶことになります。
特に、企業型DCの運用商品ラインナップ数は法令で限られているため、運営管理機関選びは非常に重要です。
⑤毎月かかる手数料の有無
1.iDeCo:加入時の初期費用に加え、国民年金基金連合会や運営管理機関に支払う口座管理手数料が毎月個人負担で発生します。
2.企業型DC:口座管理手数料は基本的に企業が福利厚生費として負担してくれます。
3.NISA:多くの金融機関で口座管理手数料が無料となっており、コストを抑えて運用を始めやすいのが特徴です。
4. 50代から確定拠出年金・NISAを始めるメリット
50代になると「今から資産形成を始めても遅いのではないか」と考える方も少なくありませんが、この年代だからこそ得られる具体的なメリットが存在します。

確定拠出年金は節税効果をすぐに実感できる
50代は、キャリアの中で所得がピークを迎える方が多い年代です。
iDeCoを利用する場合、掛金が全額所得控除となり、所得税・住民税が軽減されます。この節税効果は、運用成果とは別で確実に得られるリターンであり、年末調整で還付金として実感できる場合があります。
企業型DCの場合、掛金が非課税で拠出されるため、そもそも課税所得から除外され、所得税・住民税の負担が軽減されます。こちらは還付金としてではなく、毎月の給与計算で税金が引かれない形で効果が表れます。
NISAは運用期間に縛りがなく柔軟な資産形成が可能
NISAは制度が恒久化され、非課税で商品を保有できる期間も無期限になりました。
50代から始めても、退職後も運用を継続し、生活費の足しとして必要な分だけ取り崩したり、さらに資産を成長させたりといった柔軟な使い方が可能です。人生100年時代といわれる現代において、退職後の生活を見据えた長期的な資産管理のツールとして非常に有効です。
複利効果を活かして効率的に資産を増やせる
運用で得た利益を元本に加えて再投資する「複利効果」は、投資期間が長くなるほど大きくなります。50代からのスタートでも、仮に65歳まで15年間運用すれば、複利効果を十分に活かすことが可能です。
また、元本が大きいほど複利の効果は表れやすくなるため、退職金などまとまった資金をNISAで運用し、長期で保有を続けることも考えられます。

5. 【目的別】50代のあなたに合うのは確定拠出年金?それともNISA?
確定拠出年金とNISA、それぞれの制度の特徴を理解した上で、次はご自身の具体的な目的に合わせてどちらがより適しているかを考えていきましょう。

老後資金を確実に準備したいなら確定拠出年金が向いている
資産形成の目的が「老後の生活資金を確実に準備すること」に絞られるのであれば、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)が最も適しています。
原則として60歳まで資金を引き出せないという「ロック機能」により、途中で他の目的に使ってしまう誘惑に駆られることなく、節税効果も得られるため、着実に老後資金を積み立てることが可能です。
教育費やリフォームなど近い将来の出費に備えるならNISAが最適
数年後から10年後といった比較的近い将来に予想される出費に備えたい場合には、NISAが最適です。子どもの大学院進学費用や結婚資金の援助、自宅のリフォーム、車の買い替えなど、50代には様々なライフイベントが考えられます。
NISAはいつでも必要な時に資産を売却して現金化できる流動性の高さが魅力です。
6. まとめ
50代からの資産形成は決して遅くなく、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)とNISAを賢く使い分けることで、効率的に将来への備えをすることが可能です。
多くの場合、企業型DCとNISAを併用することが、節税と柔軟性を両立させる最適な選択肢となります。

ご自身のライフプランや資産形成の目的を明確にし、60歳以降の豊かなセカンドライフの実現に向けて、今から着実な一歩を踏み出しましょう。
日本企業型確定拠出年金センターでは、企業担当者のみなさまに、導入に関する個別相談を無料で行っています。他の制度との違いについても詳しくお伝えできますので、ぜひ一度お問合せください。
よくある質問
Q 50代の役員や従業員が多いのですが、今から導入してもメリットはありますか?
A はい、大きなメリットがあります。
50代は一般的に給与が高く、その分税金の負担も重くなっています。企業型DCの掛金は所得税・住民税の対象外となるため、所得の高い50代こそ高い節税効果(手取りの増加)を実感できます。
Q 社長や役員も企業型DCに加入できますか?
A 60 歳未満の厚生年金保険被保険者であれば、役職に関係なく社長や役員でも加入できます。
もちろん、掛け金は全額損金計上できます。拠出限度年齢の引き上げを行った場合は拠出限度年齢まで加入できます。
Q 企業型DCを導入しても、社員はNISAを続けられますか?
A はい、問題なく併用可能です。
記事でも解説した通り、老後資金(節税重視)は「企業型DC」、教育費や急な出費(流動性重視)は「NISA」というように、目的別に使い分けることが推奨されています。
会社として制度を用意することで、社員の資産形成の選択肢を広げることができます。
お問合せ・ご相談はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:050-3645-9040
※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。




















