確定拠出年金で外国株式100%はおすすめ?リスクと注意点を解説

確定拠出年金で外国株式100%はおすすめ?リスクと注意点を解説
確定拠出年金(通称:iDeCoや企業型DC、401k)の運用において、海外株式に100%投資する積極的なポートフォリオが注目されています。 高いリターンが期待できる反面、相応のリスクも伴うため、誰にでもおすすめできるわけではありません。
この記事では、外国株式100%で運用するメリットと注意点を解説し、自身がこの投資方法に向いているか判断するための情報を提供します。
自分に合った運用方法を見つけることが、長期的な資産形成の成功につながります。
1. なぜ確定拠出年金のポートフォリオで外国株式が注目されるのか
iDeCoや企業型確定拠出年金といった確定拠出年金は、老後資金形成を目的とした長期運用が前提の制度です。

その運用商品の選択肢の中で、世界経済の成長を背景に、国内資産よりも高いリターンを期待できる外国株式が注目を集めています。
特に、数十年単位での運用となる確定拠出年金の特性上、短期的な価格変動リスクを取りながらでも、将来の大きな資産成長を目指す積極的な運用戦略として、外国株式は有力な選択肢となっています。
2. 確定拠出年金を外国株式100%で運用する3つのメリット
確定拠出年金の資産をすべて外国株式で運用する戦略は非常に積極的ですが、その分大きなメリットも期待できます。
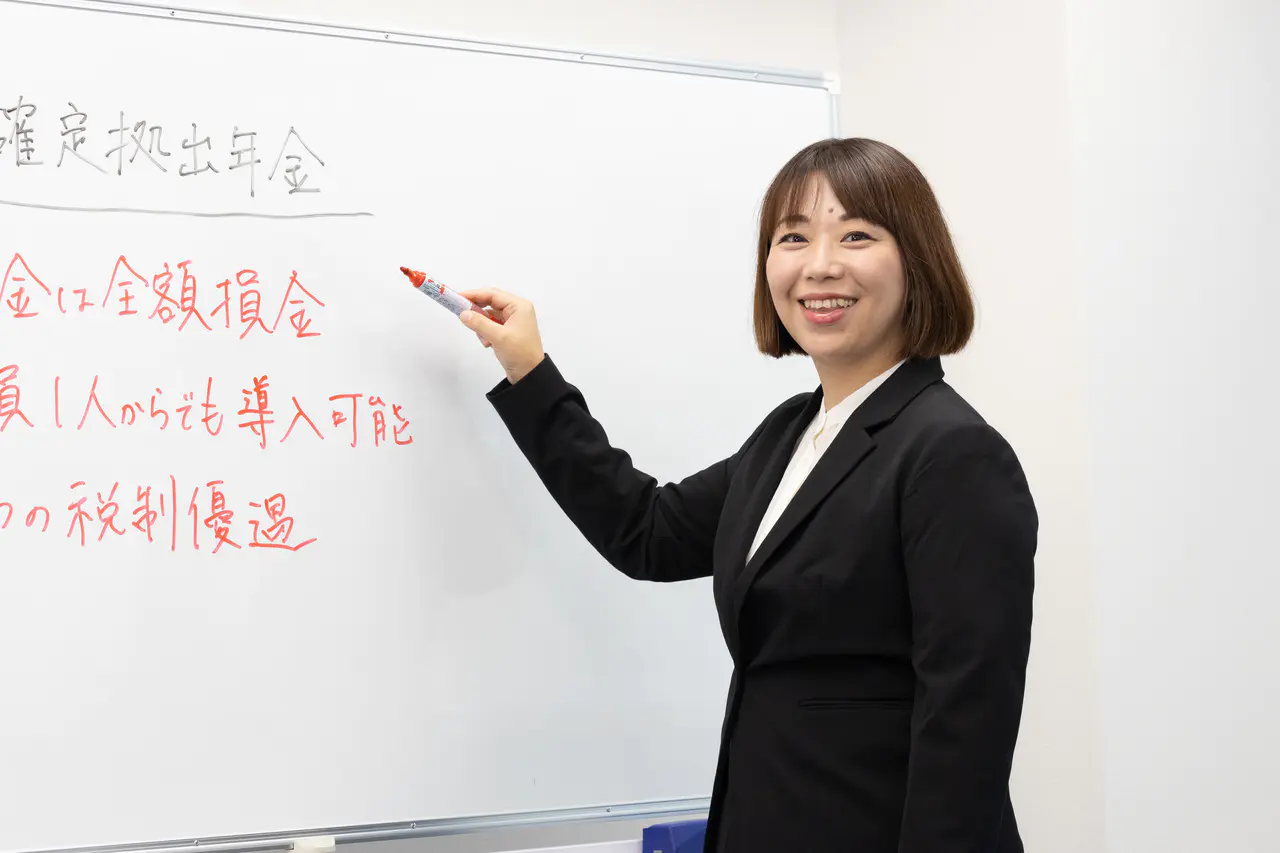
世界経済全体の成長を取り込める点や、インフレの対策になる点など、将来の資産を大きく増やす可能性を秘めています。 ここでは、外国株式100%という資産配分がもたらす具体的な3つのメリットを掘り下げていきます。
世界経済の成長の恩恵を大きく受けられる
世界の人口は増加傾向にあり、特に新興国を中心に経済は成長を続けています。 外国株式への投資は、こうした世界全体の経済成長の恩恵を直接的に受けることにつながります。
日本の経済が長期的に停滞している状況と比較して、グローバルな視点を持つことでより高い成長ポテンシャルを捉えることが可能です。 米国をはじめとする先進国や、成長著しい新興国の企業の株式に投資することで、その企業の利益成長が自身の資産増加に直結します。
特定の国や地域に限定せず、世界で事業を展開する企業の成長を取り込めるのが大きな魅力です。
長期的に高いリターンを期待できる
株式は、債券や預貯金といった他の資産クラスと比較して、長期的には高いリターンが期待できる資産です。 特に外国株式市場は、国内市場よりも多様な成長企業が存在し、市場規模も大きいため、より高い収益機会が見込まれます。
確定拠出年金のように、原則60歳まで引き出せない長期運用が前提の制度では、短期的な価格変動を乗り越えて、複利効果を最大限に活かすことが可能です。
数十年にわたる運用期間があれば、一時的な下落局面があっても、その後の回復と経済成長によって資産を大きく増やすことが期待できます。
3. 把握しておくべき外国株式100%運用の主なリスク
外国株式100%での運用は高いリターンが期待できる反面、相応のリスクを伴います。

資産が大きく変動する可能性や為替の動き、そしてそれに伴う心理的な負担など、事前に理解しておくべき重要な点があります。
これらのリスクを正しく把握し、自身が許容できる範囲内であるかを見極めることが、長期的な資産形成を成功させるための鍵となります。
資産価値の変動幅(ボラティリティ)が非常に大きい
株式は一般的に価格変動が大きい資産ですが、外国株式100%というポートフォリオは、その中でも特に変動幅(ボラティリティ)が大きくなる傾向があります。 世界的な経済危機や特定の国の政情不安などが発生した場合、株価が短期間で数十パーセント下落することも珍しくありません。
債券などの比較的安定した資産を組み入れていないため、市場の動揺が直接資産価値に反映されます。
資産が大きく増える可能性がある一方で、同じくらい大きく減少する可能性もあることを理解しておく必要があります。
為替レートの変動がリターンに影響する
外国株式への投資には、株価の変動リスクに加えて為替変動リスクが伴います。 投資対象の株式の価格が上昇しても、為替レートが円高に動けば、円換算でのリターンは減少、あるいはマイナスになる可能性があります。
例えば、1ドル150円の時に投資した資産が、株価は変わらずに1ドル130円になると、円ベースでの資産価値は約13%減少します。
逆に円安はリターンを押し上げる要因となりますが、このように為替の動きが自身の意図とは別に損益に大きな影響を与える点は、常に意識しておくべきリスクです。
相場急落時に心理的な負担を感じやすい
資産を外国株式100%で運用していると、世界的な株価急落の局面で資産額が大幅に減少することがあります。
確定拠出年金は長期運用が前提であり、短期的な下落で慌てて売却すべきではないと頭では理解していても、実際に自身の資産が大きく目減りしていく状況を目の当たりにすると、大きな不安や焦りを感じるものです。 その結果、冷静な判断ができなくなり、本来であれば長期的な成長が見込める資産を底値で手放してしまう「狼狽売り」につながる可能性があります。

4. 確定拠出年金で外国株式100%の運用が向いている人
外国株式100%という積極的な運用方法は、すべての人に適しているわけではありません。

高いリスクを許容できる特定の条件を満たした人にとっては、将来の資産を大きく増やすための有効な選択肢となり得ます。 具体的には、運用に充てられる期間、リスクに対する考え方、そして他の資産状況などが判断の基準になります。
ここでは、どのような人がこの運用スタイルに向いているのかを解説します。
20代〜30代で長期的な運用期間を確保できる人
確定拠出年金の受け取り開始は原則60歳以降であり、20代や30代の人は30年以上の長期的な運用期間を確保できます。 運用期間が長ければ、途中で市場が大きく下落したとしても、その後の回復・成長期間を十分に待つことが可能です。
また、若い世代は一般的に収入が今後増えていく可能性が高いため、積立額を増やしていくこともできます。
時間を味方につけることで、複利効果を最大限に活用し、短期的な価格変動リスクを乗り越えて大きなリターンを狙う積極的な運用が選択しやすくなります。
値下がりの局面でも冷静に対応できるリスク許容度の高い人
リスク許容度とは、資産運用においてどの程度の価格変動や損失に耐えられるかを示す度合いのことです。 外国株式100%の運用では、資産価値が一時的に30%や40%減少する可能性も考慮しておく必要があります。
そのような状況でも、長期的な視点を忘れずに積立を継続できる、精神的な強さが求められます。 日々の値動きに一喜一憂せず、むしろ下落局面を「安く買えるチャンス」と捉えられるような、高いリスク許容度を持つ人に向いている運用方法です。
自身の性格や投資経験を客観的に評価することが重要です。
確定拠出年金以外にも安定した資産を持っている人
老後資金のすべてを確定拠出年金だけで準備しているわけではなく、預貯金や個人年金保険、あるいは安定運用を目的とした別の投資信託など、他の金融資産を十分に保有している人も積極的な運用を選択しやすいです。
確定拠出年金のポートフォリオがリスクの高い外国株式100%であっても、資産全体で見たときにはリスクが分散されている状態になります。
5. 外国株式100%に不安がある場合のポートフォリオ調整法
外国株式100%という運用は魅力的である一方、リスクが高いと感じる人も少なくありません。

その場合は、無理に一つの資産に集中させるのではなく、他の資産を組み合わせてリスクを分散させることが賢明です。 資産の割合や比率を調整することで、自身のリスク許容度に合ったポートフォリオを構築できます。
ここでは、リスクを抑えつつ、安定的な資産成長を目指すための具体的な調整法を紹介します。
年齢が上がるにつれて債券の比率を高める
一般的な資産運用の考え方として、年齢が上がり、資産の受け取り時期が近づくにつれて、リスクの高い資産の割合を減らし、安定的な資産の割合を増やすことが推奨されます。 具体的には、外国株式の比率を徐々に下げ、代わりに国内外の債券の比率を高めていく方法です。
債券は株式に比べて価格変動が小さく、安定した利息収入が期待できるため、ポートフォリオ全体の値動きを穏やかにする効果があります。
50代に差し掛かったら株式と債券の比率を半々にするなど、自身の年齢や目標額に応じて定期的に資産配分を見直すことが重要です。
国内株式や不動産(REIT)を加えて分散効果を狙う
分散投資の基本は、異なる値動きをする資産を組み合わせることです。 外国株式だけでなく、国内株式や国内外の不動産投資信託(REIT)をポートフォリオに加えることで、より高い分散効果が期待できます。
例えば、外国経済が不調で外国株式が下落しても、日本経済が好調であれば国内株式がそれを補うといった効果が見込めます。 REITは株式とは異なる値動きをすることが多く、不動産からの賃料収入を原資とするため、インフレに強い資産としても知られています。
複数の資産クラスに分散させることで、特定の市場の不振が資産全体に与える影響を和らげることができます。
6. 企業型DCの選択制を導入するメリット
企業型確定拠出年金(企業型DC)の中でも、従業員が任意で加入や掛金拠出を選択できる「選択制DC」は、企業と従業員の双方にとってメリットの大きい制度です。

従業員の資産形成を支援しながら、企業の掛金負担を抑えることが可能で、福利厚生の充実にもつながります。
ここでは、企業が選択制DCを導入することで得られる具体的なメリットについて解説します。
役員・従業員の将来の資産形成をサポート
選択制DCを導入することで、企業は役員や従業員に対して、税制優遇を受けながら老後資金を準備する機会を提供できます。公的年金だけでは将来の生活に不安を感じる人が増える中、会社が主体となって資産形成の場を用意することは、従業員のエンゲージメント向上に繋がります。
掛金は給与所得とみなされないため、所得税・住民税が非課税(課税対象外)となり、運用益も非課税になるなど、資産を増やせる可能性があります。iDeCo(イデコ)の掛金は所得控除の対象ですが、企業型DCの掛金は拠出時に非課税となる点が大きな違いです。
企業型DCの場合は口座管理手数料は福利厚生費で会社負担となるため、iDeCoよりも効率的に資産を増やせる可能性があります。
会社の掛金負担を抑えつつ福利厚生を充実させる
選択制DCでは、従来の給与の一部を「生涯設計手当」などとし、その手当をそのまま受け取るか、事業主掛金として拠出するかを従業員自身が選択します。
これにより、企業は新たな掛金負担を抑えながら、確定拠出年金という魅力的な福利厚生制度を導入できます。
人材採用や定着率の向上においても、充実した福利厚生は企業の競争力を高める重要な要素となります。
退職金代わりにもなる確実性の高い老後資金の準備
従来の退職金制度は、企業の業績によっては将来的に減額されたり、制度自体が維持できなくなったりするリスクがあります。 一方、確定拠出年金は個人の口座で資産が管理されるため、会社の経営状況に左右されることなく、確実に自身の老後資金として積み立てていくことが可能です。
選択制DCを退職金制度の代替、あるいは補完として位置づけることで、従業員はより計画的に、かつ安心して老後のための資産を準備できます。

7. まとめ
確定拠出年金における外国株式100%での運用は、世界経済の成長を背景に高いリターンが期待できる一方で、価格変動や為替の大きなリスクを伴う積極的な戦略です。
この運用方法が適しているのは、長期的な運用期間を確保できる若年層や、高いリスク許容度を持つ人、そして確定拠出年金以外にも資産を有している人に限られます。

リスクが高いと感じる場合は、債券や国内株式を組み入れたり、全世界株式ファンドを活用したりして、自身に合ったポートフォリオを構築することが重要です。
最終的には、自身の年齢や資産状況、リスクに対する考え方を総合的に考慮し、納得のいく資産配分を決定する必要があります。
日本企業型確定拠出年金センターでは、企業担当者のみなさまに、制度導入から運営までサポートさせていただきます。ぜひ一度お問合せください。
お問合せ・ご相談はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:050-3645-9040
※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。
よくある質問(FAQ)
Q 加入者1名でも企業型を導入できますか?
A 1名からでも導入可能です。
確定拠出年金法では企業型の設立に人数要件はありません。厚生年金の適用事業所であれば導入可能です。
Q 確定拠出年金の加入者数や導入している実施事業主(所)数は?
A 企業型DCの加入者数は8,053千人です。実施事業所数は47,138社です。 ※2023年3月末時点(厚生労働省HPより)
iDeCoの加入者数は以下のとおりです。
国民年金第1号被保険者(自営業者等):362,317人
国民年金第2号被保険者(給与所得者等):2,880,478人
国民年金第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者):147,068人
国民年金任意加入被保険者:9,748人
登録事業所数は821,492事業所です。
※2024年7月末時点(iDeCo公式サイトより)
Q 役員も企業型に加入できますか?
A 60 歳未満の厚生年金保険被保険者であれば、役職に関係なく社長や役員でも加入できます。
もちろん、掛け金は全額損金計上できます。拠出限度年齢の引き上げを行った場合は拠出限度年齢まで加入できます。
例)拠出限度年齢65歳の場合 65歳未満の厚生年金被験者




















