企業年金が支給停止となる理由は?企業型Dが受け取れないケースも解説します

企業年金が支給停止となる理由は?企業型DCが受け取れないケースも解説します
企業年金は、老齢基礎年金や老齢厚生年金といった公的年金に上乗せされる形で支給され、退職後の生活を支える重要な収入源です。
しかし、退職後の働き方や特定の条件によっては、この企業年金の支給が一時的に停止されたり、減額されたりする場合があります。 支給停止の理由を正しく理解していないと、想定していた収入が得られず、生活設計に影響が出る可能性も否定できません。
本記事では、企業年金の支給が停止される主な理由や、収入の基準額、そして近年導入が進む企業型確定拠出年金(選択制DC)についても解説します。
1. 企業年金の支給が停止される主な理由
企業年金の支給が停止される理由は一つではありません。

多くの場合、公的年金である老齢年金の支給停止ルールに連動する形で定められています。
例えば、退職後に失業保険を受け取る場合や、定年後も働き続けて一定以上の収入がある場合などが該当します。また、それらとは別に、企業が独自に定める規約や規定によって支給条件が設けられていることもあります。
ここでは、企業年金の支給が停止される代表的な理由を3つのケースに分けて具体的に見ていきます。
雇用保険の基本手当(失業保険)を受給している
65歳未満で退職し、ハローワークで求職の申し込みをして雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となります。 これは、年金と基本手当を同時に受け取ることはできないと定められているためです。
そして、多くの企業年金は、この老齢厚生年金の支給を前提としているため、年金が停止されるのに伴い、企業年金の支給も停止される規約や規定になっていることが一般的です。 どちらを受給するかは選択制であり、基本手当の額が年金額を上回る場合は基本手当を、下回る場合は年金を選択する方が有利になります。
受給手続きを行う前に、双方の金額を比較検討することが求められます。
在職中で給与と年金の合計が基準額を超えている
60歳以降も厚生年金に加入して会社で働く場合、「在職老齢年金」という制度が適用されます。 これは、給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の月額(基本月額)の合計額が、定められた基準額を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みです。
企業年金の中には、この在職老齢年金制度による公的年金の支給停止に連動して、支給額を調整したり、支給を停止したりする規定を設けている場合があります。 つまり、働きながら得られる給与が高額であると、公的年金だけでなく企業年金も減額される可能性があるのです。
このルールは企業の年金規約や規定によって異なるため、事前の確認が不可欠です。
会社の規約や規定で定められた支給条件を満たしていない
企業年金は、法律で定められた公的年金とは異なり、企業が従業員のために任意で設けている私的年金制度です。 そのため、支給に関する詳細な条件は、それぞれの企業が定める規約や規定によって定められています。 この規約や規定の中には、特定の条件下で年金の支給を停止する旨が盛り込まれている場合があります。
例えば、退職後に競合他社へ就職した場合や、同グループ内の別会社で役員に就任した場合などが支給停止の条件として挙げられることがあります。
公的年金のルールとは関係なく、企業独自の方針で定められているため、退職後のキャリアプランを考える際には、自社の規約や規定にどのような支給停止事由が記載されているかを必ず確認しておく必要があります。
2. 収入がいくらから支給停止の対象になるのか
60歳以降も働きながら年金を受け取る場合、収入によっては年金の一部または全額が支給停止になる可能性があります。
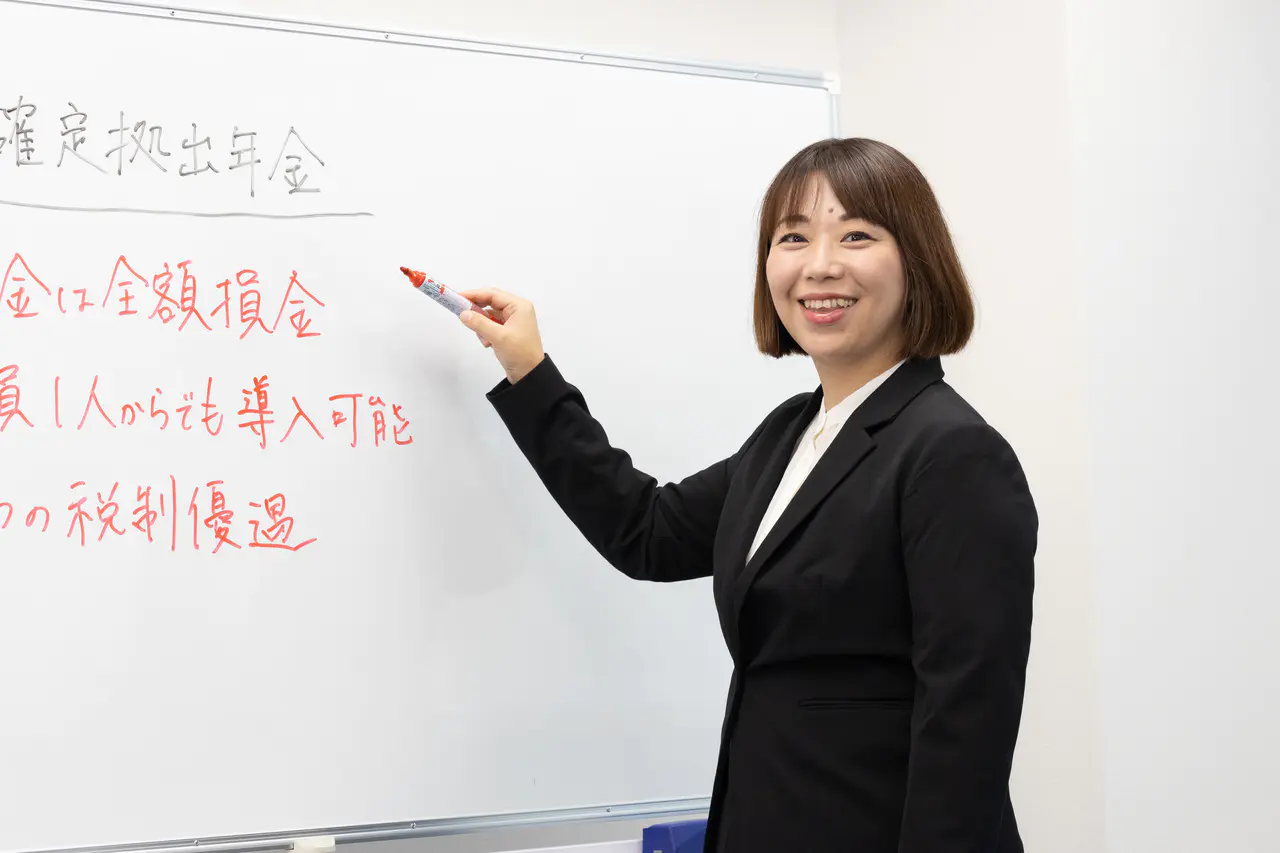
この仕組みは「在職老齢年金制度」と呼ばれ、公的年金である老齢厚生年金に適用されますが、多くの企業年金もこの制度に準じて支給調整を行うことがあります。 では、具体的にどのくらいの収入があると支給停止の対象となってしまうのでしょうか。
ここでは、その基準となる金額や計算方法について詳しく解説します。
在職老齢年金制度における支給停止基準額を解説
在職老齢年金制度では、支給停止の基準となる金額が定められています。 2025年度現在、この支給停止調整額は51万円です。 具体的には、毎月の給与と賞与から算出される「総報酬月額相当額」と、老齢厚生年金を12で割った「基本月額」の合計が51万円を超えた場合に、その超えた額の2分の1に相当する金額が、老齢厚生年金の支給額から停止されます。
例えば、合計額が60万円だった場合、51万円を超えた9万円の半額である4.5万円が毎月の年金額から差し引かれる計算になります。
この在職老齢年金の仕組みを理解しておくことは、働きながら年金をいくら受け取れるかを把握する上で非常に重要です。
3. 企業型確定拠出年金(選択制DC)が受け取れないケース
企業型確定拠出年金(選択制企DC)は、従業員が給与の一部を拠出するかを選択し、その拠出額が「事業主掛金」として積み立てられる仕組みで、運用商品を選んで資産を形成するタイプの年金制度です。

従来の企業年金とは異なり、運用成績によって将来受け取る年金額が変動するのが特徴です。
この制度は、原則として老後の資産形成を目的としているため、特定の条件を満たさない限り、途中で資産を引き出すことはできません。 また、退職や転職の際に必要な手続きを怠ると、意図せず不利益を被る可能性もあります。
ここでは、企業型DCの資産を受け取れない、あるいは引き出せない代表的なケースについて説明します。
転職や退職の際に移換手続きを忘れている
企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していた人が会社を退職、または転職した場合、それまで積み立ててきた年金資産を次の制度へ移す「移換」という手続きが必要です。 具体的には、退職後6ヶ月以内に、転職先の企業型DCや個人型確定拠出年金(iDeCo)などへ資産を移さなければなりません。
この期間内に手続きを行わないと、年金資産は国民年金基金連合会に「自動移換」されてしまいます。 自動移換の状態になると、資産は現金化され、その後は一切の運用が行われません。 さらに、管理手数料だけは継続的に差し引かれるため、年金資産が徐々に目減りしていくというデメリットが生じます。
せっかく築いた資産を守るためにも、退職時の移換手続きは忘れずに行うことが重要です。
4. 企業年金の支給停止で損をしないための確認事項
企業年金は退職後の生活を支える大切な資金ですが、予期せぬ支給停止によって計画が狂ってしまう事態は避けたいものです。

特に定年後も働くことを考えている場合、どのような働き方をすると年金に影響が出るのかを事前に把握しておくことが極めて重要になります。
支給停止のリスクを回避し、受け取れるはずの年金を確実に受け取るためには、あらかじめ確認しておくべきポイントがあります。
ここでは、後で「知らなかった」と後悔しないために、事前に押さえておきたい2つの重要な確認事項を解説します。
勤務先の企業年金の規約や規定をあらかじめ読んでおく
企業年金の支給条件や支給停止に関するルールは、法律で一律に定められているわけではなく、各企業が独自に作成した規約や規定に基づいています。 そのため、自分の企業年金がどのような場合に支給停止になるのかを正確に知るためには、この規約や規定を確認することが最も確実な方法です。
規約や規定には、在職老齢年金制度との連動の有無や、競合他社への就職といった企業独自の支給停止事由などが明記されています。 退職後の働き方を具体的に検討する前に、まずは自社の規約や規定を取り寄せ、内容をしっかりと読み込んでおくことが、将来の資金計画を立てる上での第一歩となります。 不明な点があれば、人事部や年金担当者に問い合わせることも重要です。
不明点は年金事務所や専門家に相談する
企業年金の規約や規定は、在職老齢年金などの公的年金制度のおいて、内容が複雑で専門的な用語も多く使われています。 自分だけで規約や規定を読んでも、正確に理解するのが難しいと感じることも少なくありません。
特に、退職後の働き方が年金にどう影響するのかといった判断は、個々の状況によって異なるため、自己判断は禁物です。 もし規約や規定の内容や制度の仕組みで少しでも疑問や不安な点があれば、会社の年金担当部署に質問するほか、お近くの年金事務所の窓口で相談するのがよいでしょう。
また、より個別具体的なアドバイスが必要な場合は、社会保険労務士やファイナンシャルプランナーといった年金の専門家に相談することも有効な手段です。
5. 企業型DCの選択制を導入するメリット
企業型確定拠出年金(企業型DC)の中でも、従業員が任意で加入や掛金拠出を選択できる「選択制DC」は、企業と従業員の双方にとってメリットの大きい制度です。

従業員の資産形成を支援しながら、企業の掛金負担を抑えることが可能で、福利厚生の充実にもつながります。
ここでは、企業が選択制DCを導入することで得られる具体的なメリットについて解説します。
役員・従業員の将来の資産形成をサポート
選択制DCを導入することで、企業は役員や従業員に対して、税制優遇を受けながら老後資金を準備する機会を提供できます。公的年金だけでは将来の生活に不安を感じる人が増える中、会社が主体となって資産形成の場を用意することは、従業員のエンゲージメント向上に繋がります。
掛金は給与所得とみなされないため、所得税・住民税が非課税(課税対象外)となり、運用益も非課税になるなど、資産を増やせる可能性があります。iDeCo(イデコ)の掛金は所得控除の対象ですが、企業型DCの掛金は拠出時に非課税となる点が大きな違いです。
企業型DCの場合は口座管理手数料は福利厚生費で会社負担となるため、iDeCoよりも効率的に資産を増やせる可能性があります。
会社の掛金負担を抑えつつ福利厚生を充実させる
選択制DCでは、従来の給与の一部を「生涯設計手当」などとし、その手当をそのまま受け取るか、事業主掛金として拠出するかを従業員自身が選択します。
これにより、企業は新たな掛金負担を抑えながら、確定拠出年金という魅力的な福利厚生制度を導入できます。
人材採用や定着率の向上においても、充実した福利厚生は企業の競争力を高める重要な要素となります。
退職金代わりにもなる確実性の高い老後資金の準備
従来の退職金制度は、企業の業績によっては将来的に減額されたり、制度自体が維持できなくなったりするリスクがあります。
一方、確定拠出年金は個人の口座で資産が管理されるため、会社の経営状況に左右されることなく、確実に自身の老後資金として積み立てていくことが可能です。
選択制DCを退職金制度の代替、あるいは補完として位置づけることで、従業員はより計画的に、かつ安心して老後のための資産を準備できます。

6. まとめ
企業年金の支給が停止される主な理由には、公的年金制度と連動するケースと、企業独自の規約や規定に基づくケースが存在します。
具体的には、雇用保険の基本手当受給や、在職中の給与と年金の合計が在職老齢年金制度の基準額(2025年度は51万円)を超える場合が挙げられます。

また、企業型確定拠出年金(企業型DC)では、原則60歳まで引き出せないほか、退職時に移換手続きを怠ると資産が目減りするリスクがあります。 これらの予期せぬ支給停止を避けるためには、退職後の働き方を決める前に、まず勤務先の企業年金の規約や規定を熟読し、支給停止の条件を正確に把握することが不可欠です。
内容が複雑で理解が難しい場合は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談し、自身の状況に合わせたアドバイスを受けることが、安定した老後設計につながります。
日本企業型確定拠出年金センターでは、企業担当者のみなさまに、制度導入から運営までサポートさせていただきます。ぜひ一度お問合せください。
お問合せ・ご相談はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:050-3645-9040
※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。
よくある質問(FAQ)
Q 加入者1名でも企業型を導入できますか?
A 1名からでも導入可能です。
確定拠出年金法では企業型の設立に人数要件はありません。厚生年金の適用事業所であれば導入可能です。
Q 確定拠出年金の加入者数や導入している実施事業主(所)数は?
A 企業型DCの加入者数は8,053千人です。実施事業所数は47,138社です。 ※2023年3月末時点(厚生労働省HPより)
iDeCoの加入者数は以下のとおりです。
国民年金第1号被保険者(自営業者等):362,317人
国民年金第2号被保険者(給与所得者等):2,880,478人
国民年金第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者):147,068人
国民年金任意加入被保険者:9,748人
登録事業所数は821,492事業所です。
※2024年7月末時点(iDeCo公式サイトより)
Q 役員も企業型に加入できますか?
A 60 歳未満の厚生年金保険被保険者であれば、役職に関係なく社長や役員でも加入できます。
もちろん、掛け金は全額損金計上できます。拠出限度年齢の引き上げを行った場合は拠出限度年齢まで加入できます。
例)拠出限度年齢65歳の場合 65歳未満の厚生年金被験者




















