企業型DC・iDeCo(確定拠出年金)の評価損益がマイナス表示は危険?原因と対処法を解説

企業型DC・iDeCo(確定拠出年金)の評価損益がマイナス表示は危険?原因と対処法を解説
確定拠出年金(企業型DCやiDeCo)で資産運用を始めると、評価損益がマイナスになる場面に直面することがあります。
iDeCoとは、自分で運用商品を選び、その運用成果によって将来受け取る年金額が変わる私的年金制度のことです。 大切な老後資金が目減りしているように見えると不安になりますが、その原因と適切な対処法を知ることで、冷静に対応できます。
この記事では、評価損益がマイナスになる理由と、長期的な資産形成を成功させるための具体的な対策を解説します。
1. 確定拠出年金の評価損益がマイナスでも慌てる必要はありません
確定拠出年金の評価損益がマイナスになっていても、すぐに元本割れを心配して慌てる必要はありません。

この制度は60歳以降に受け取る資金を準備するためのものであり、長期的な運用が前提です。 短期的な価格の上下で一喜一憂せず、長期的な視点を持つことが肝心です。
むしろ価格が下落している局面は、同じ掛金でより多くの口数を購入できるチャンスでもあります。

2. なぜ?確定拠出年金の評価損益がマイナスになる5つの理由
評価損益がマイナスになる背景には、市場全体の動きから個人の運用スタイルまで、いくつかの理由が考えられます。
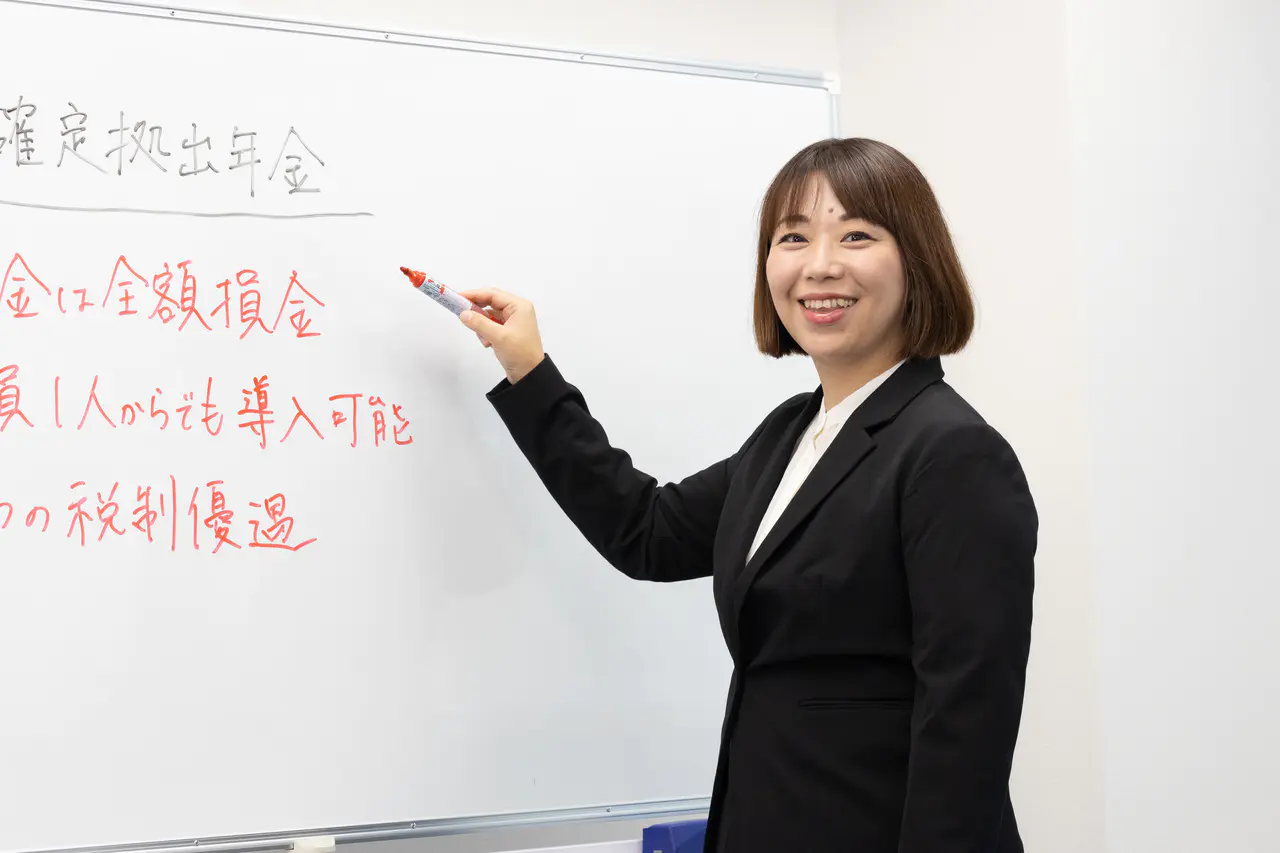
確定拠出年金(DC)の資産は、原則として60歳から老齢給付金として受け取ることができます。
今回の法改正で、この受給開始時期の上限が70歳から75歳に引き上げられました。 つまり、加入者は60歳から75歳になるまでの15年間の中から、自身のライフプランに合わせて最適なタイミングを選んで受給を開始できます。
加入資格の上限と受給開始時期の上限は異なるため、それぞれの制度内容を正しく理解しておくことが重要です。
理由1:投資している金融商品の価格が下落している
評価損益がマイナスになる最も直接的な原因は、購入した投資信託などの金融商品の基準価額そのものが下落していることです。 国内外の株式や債券の価格は、世界経済の動向、各国の金融政策、地政学的な出来事など、多岐にわたる要因の影響を受けて日々変動します。
市場全体が調整局面に入れば、多くの商品の価格が一時的に購入時を下回り、評価損益はマイナスになります。
しかし、経済は長期的に成長する傾向があるため、価格の下落はあくまで一時的な現象と捉え、将来プラスに転じることを見据えた運用が求められます。
理由2:リスクの高い商品に資産が偏っている
高いリターンが期待できる株式ファンドなど、価格変動リスクの大きい金融商品に資産が偏っている場合、市場が下落した際の評価損益のマイナス幅も大きくなる傾向があります。 特に、特定の国や業種に集中投資しているポートフォリオは、その対象の値動きに資産全体が大きく左右されてしまいます。
リスクを抑えるためには、値動きの異なる複数の資産クラス(国内株式、先進国株式、債券など)に資金を分散させることが基本です。
これにより、ある資産が値下がりしても他の資産でカバーし、全体の損失を和らげる効果が期待できます。
理由3:短期的な価格変動で商品を頻繁に売買している
確定拠出年金は、老後資金を準備するための長期投資を前提とした制度です。 日々の値動きに一喜一憂し、商品を頻繁に売買する(スイッチングする)ことは、かえって損失を拡大させる原因になりかねません。
市場のタイミングを正確に読んで売買を繰り返すことはプロの投資家でも困難であり、感情的な判断は「高値掴み」や「安値売り」につながりがちです。 短期的なマイナスに焦って売却すると、その後の価格回復の恩恵を受けられなくなります。
どっしりと構え、積立を継続することが長期的な成功の鍵を握ります。
理由4:元本確保型の商品で運用コストがリターンを上回っている
定期預金や保険商品などの元本確保型の商品は、元本が保証される安心感がある反面、得られるリターンは極めて低い水準です。 確定拠出年金では、加入しているだけで口座管理手数料などのコストが毎月発生します。
もし、元本確保型商品の利息がこれらの手数料を下回っている場合、運用リターンよりもコスト負担が大きくなり、資産は少しずつ目減りしていきます。
安全性を最優先するあまり、リターンを生まない商品だけで運用していると、インフレによって資産の実質的な価値が下がってしまうリスクも抱えることになります。
理由5:為替相場の変動で円換算の評価額が下がっている
外国の株式や債券を組み入れている投資信託は、為替相場の変動からも影響を受けます。 投資先の資産価格が現地通貨ベースで上昇していても、その国の通貨に対して円高が進行すると、円に換算した際の評価額は下がってしまいます。
例えば、1ドル150円の時に投資した資産が、為替変動で1ドル140円になれば、それだけで円建ての資産価値は約7%減少することになります。 海外資産に投資する際は、こうした為替変動リスクが存在することを理解しておく必要があります。

3. 評価損益がマイナスになった時に試したい3つの対策
評価損益がマイナス表示されると、不安から性急な行動を取りがちですが、まずは冷静に状況を分析することが重要です。

確定拠出年金は長期的な視点が基本であり、時には何もしないで積立を続けることが最善の策となる場合もあります。一方で、現在の運用方法が自分の考えとずれていないかを確認する良い機会とも捉えられます。
ここでは、評価損益がマイナスになった際に検討すべき、具体的な3つの対策を紹介します。
対策1:まずは長期的な視点で運用を続ける
確定拠出年金の運用で最も大切なことは、短期的な市場の変動に動揺せず、当初の計画通りに積立投資を継続することです。
価格が下落している局面では、毎月の掛金でより多くの口数を購入できるため、将来、市場が回復した際に大きなリターンを生む原動力となります。 これは「ドルコスト平均法」と呼ばれる手法の効果であり、長期の積立投資における大きなメリットです。
受給開始までまだ時間的な余裕がある場合は、目先のマイナス評価を気にしすぎず、長期的な資産の成長を信じて運用を続けることが合理的な判断といえます。
対策2:資産配分(アセットアロケーション)を再確認する
評価損益のマイナスが続くようであれば、現在の資産配分が自分の年齢やリスク許容度に合っているかを見直す良い機会です。
運用開始時には積極的な配分で問題なくても、年齢を重ねるにつれて、より安定性を重視した運用に切り替えたいと考えるのは自然なことです。 保有している商品が株式や海外資産など、リスクの高いものに偏りすぎていないかを確認しましょう。
定期的に資産配分を点検し、必要に応じてリバランスを行うことで、長期的に安定した資産形成を目指すことが可能になります。
対策3:「スイッチング」で保有商品の構成を見直す
資産配分を見直した結果、保有している商品の構成を変更する必要があると判断した場合には、「スイッチング」という手続きを行います。 スイッチングとは、現在保有している金融商品を一度売却し、その資金で新たに別の商品を購入することです。
例えば、積極的な運用を行う株式ファンドの比率を下げ、安定的な値動きが期待できる債券ファンドの比率を高めることで、ポートフォリオ全体のリスクを抑制できます。 ただし、市場の動向を読んで頻繁にスイッチングを繰り返すことは推奨されません。

4. 今後の損失リスクを抑えるための運用商品の選び方
これまでの経験を踏まえ、将来の損失リスクをできるだけ抑えながら資産形成を進めるには、自分に合った運用商品を選ぶプロセスが極めて重要です。

そのためには、まず自分がどの程度のリスクを受け入れられるのかを客観的に把握し、それに基づいた明確な運用方針を立てる必要があります。
ここでは、今後の運用で後悔しないための、具体的な商品選びの考え方について解説します。
自分のリスク許容度がどの程度か把握する
リスク許容度とは、資産運用を行う上で、どの程度の価格のブレや一時的な損失を受け入れられるかという度合いを指します。 これは年齢、収入、資産状況、投資経験、そして性格などによって人それぞれ異なります。
一般的に、運用期間を長く確保できる20代や30代はリスク許容度が高く、受給開始年齢が近い50代以降は低くなる傾向があります。 まずは、仮に資産が10%や20%下落した場合、冷静に積立を継続できるかを自問自答してみましょう。
金融機関のウェブサイトにある診断ツールなどを活用して、客観的に自分のリスク許容度を把握することが、適切な商品選びの出発点になります。
運用方針に応じて安定型と積極型の割合を決める
自身のリスク許容度を把握できたら、次はその度合いに応じて具体的な商品の組み合わせを考えます。 確定拠出年金で提供される商品は、大きく分けて元本確保型の預金や保険などの「安定型」と、株式やREIT(不動産投資信託)などを中心とした「積極型」に分類できます。
リスク許容度が低い方は安定型の比率を高めに、高い方は積極型の比率を高めに設定するのが基本です。 例えば、「安定型7割、積極型3割」といったように、自分の心地よいと感じるバランスを見つけましょう。

5. iDeCoよりもメリットがある?選択制企業型DCをおすすめする理由
老後資金を準備する確定拠出年金には、個人で加入するiDeCoと、勤務先の企業が導入する企業型DCがあります。

特に、給与の一部を掛金にするか、そのまま給与として受け取るかを選べる「選択制企業型DC」は、iDeCoとは異なる税制上のメリットがあり、より効率的な資産形成を目指せます。 iDeCoも企業型DCも、公的年金に上乗せする私的な年金制度であり、その役割は同じです。
しかし、掛金の拠出方法と税制上の扱いに大きな違いがあります。
選択制DCは掛金が「給与算定対象外」!iDeCoとの税制上の大きな違い
確定拠出年金の掛金にかかる税制優遇は、iDeCoと企業型DCで仕組みが異なります。 iDeCoの掛金:全額が所得控除の対象です。納めた税金が年末調整などで戻ってくる仕組みです。
企業型DCのうち、会社掛金に上乗せするマッチング拠出も、iDeCoと同じく所得控除として扱われます。 選択制企業型DCの掛金:給与の一部を掛金とするため、この掛金分は最初から給与とはみなされず、所得税・住民税の課税対象外(不課税)となります。
つまり、所得控除の対象ではありません。最初から課税されないため、より有利な税制優遇を受けられます。
会社が負担するため個人負担ゼロ!企業型DCの口座管理手数料
確定拠出年金を運用する際には、口座管理手数料などのコストが毎月発生します。 iDeCoの場合、これらの手数料はすべて加入者個人の負担となり、運用利回りから差し引かれます。
これに対して企業型DCでは、制度の運営に必要な口座管理手数料などを、会社側が福利厚生費として負担することが一般的です。
運用期間が数十年と長くなる確定拠出年金において、この手数料を個人で負担しなくて済むことは、最終的な受取額に大きなプラスの影響を与える要因となります。
簡単に老後資金準備ができる選択制DCの仕組み
選択制企業型DCは、現在の給与の一部を「生涯設計手当」などの名目で切り分け、その範囲内で掛金を拠出するか、全額を給与として受け取るかを選択する仕組みです。
iDeCoのように、新たに銀行口座を登録して毎月資金を引き落とす必要がないため、家計に新たな負担感を覚えることなく、スムーズに老後資金の準備を始められます。 給与天引きで自動的に積立が行われるため、一度設定してしまえば手間がかからず、意志の力に頼らずとも計画的な資産形成を継続しやすいという利点もあります。

【役員の方向け】 役員も全額損金で拠出できる
選択制企業型DCは、従業員だけでなく会社の役員も加入することが可能です。 役員がこの制度を利用する場合、役員報酬の一部を掛金として拠出することになります。
この拠出された掛金は、法人にとっては役員報酬の減額と同義であるため、社会保険料の算定基礎から除外され、さらに全額を損金として計上できます。 これにより、法人税の負担を軽減する効果が期待できます。

6. まとめ
確定拠出年金の評価損益がマイナスになっても、長期運用の前提を忘れなければ、過度に不安になる必要はありません。 マイナスの原因は、市場全体の動向、為替変動、あるいは自身の資産配分の偏りなど多岐にわたります。
まずは原因を冷静に分析し、短期的な値動きに惑わされず積立を継続することが基本です。

その上で、年齢やリスク許容度の変化に応じて資産配分を見直したり、必要であればスイッチングを検討したりします。 今後の運用においては、自身のリスク許容度を正しく把握し、安定型と積極型の商品を適切に組み合わせることが損失リスクの抑制に繋がります。
制度面では、選択制企業型DCも有力な選択肢となります。 確定拠出年金は原則60歳まで引き出せない 確定拠出年金(DC・iDeCo)は、原則として60歳になるまで資産を引き出すことができません(老齢給付金の受給要件を満たした場合)。この長期的な拘束があるからこそ、税制優遇を受けられる制度設計となっています。短期的な運用成績に惑わされず、長期的な視点での資産形成を意識することが重要です。
なお、企業型DCの場合、老齢給付金の受給権を満たしていても、加入者資格を喪失するまでは給付手続きに入れない点も理解しておきましょう。
















