確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の目標額はいくらがいい?わかりやすく解説します

確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の目標額はいくらがいい?わかりやすく解説します
確定拠出年金は、iDeCoや企業型(企業型確定拠出年金・401k)といった種類があり、公的年金に上乗せする私的年金として老後資金を準備するための有効な制度です。
しかし、具体的にいくらを目標金額に設定すれば良いのか悩む方も少なくありません。 この制度を最大限に活用するためには、自分自身のライフプランに基づいた目標額を明確にし、計画的に資産を形成していくことが不可欠です。
本記事では、老後に必要な資金額の目安から、具体的な目標額の計算方法、そして目標達成に向けた積立額のシミュレーションまでを分かりやすく解説します。
1. 最初に確認!老後の生活に必要となる資金額の目安
老後資金を考える上で、まず一般的な生活費の目安を知ることが第一歩となります。

生命保険文化センターの調査によると、夫婦二人が老後生活を送る上で最低限必要と考える生活費は月額平均で約23.2万円、ゆとりある生活を望む場合は約37.9万円という結果が出ています。
60歳で定年退職し、90歳まで生きると仮定した場合、30年間で数千万円単位の資金が必要になる計算です。

2. 【3ステップ】確定拠出年金で準備する目標額の決め方
老後のための資産形成を始めるにあたり、漠然と積み立てるのではなく、具体的な目標額を設定することが成功への鍵となります。
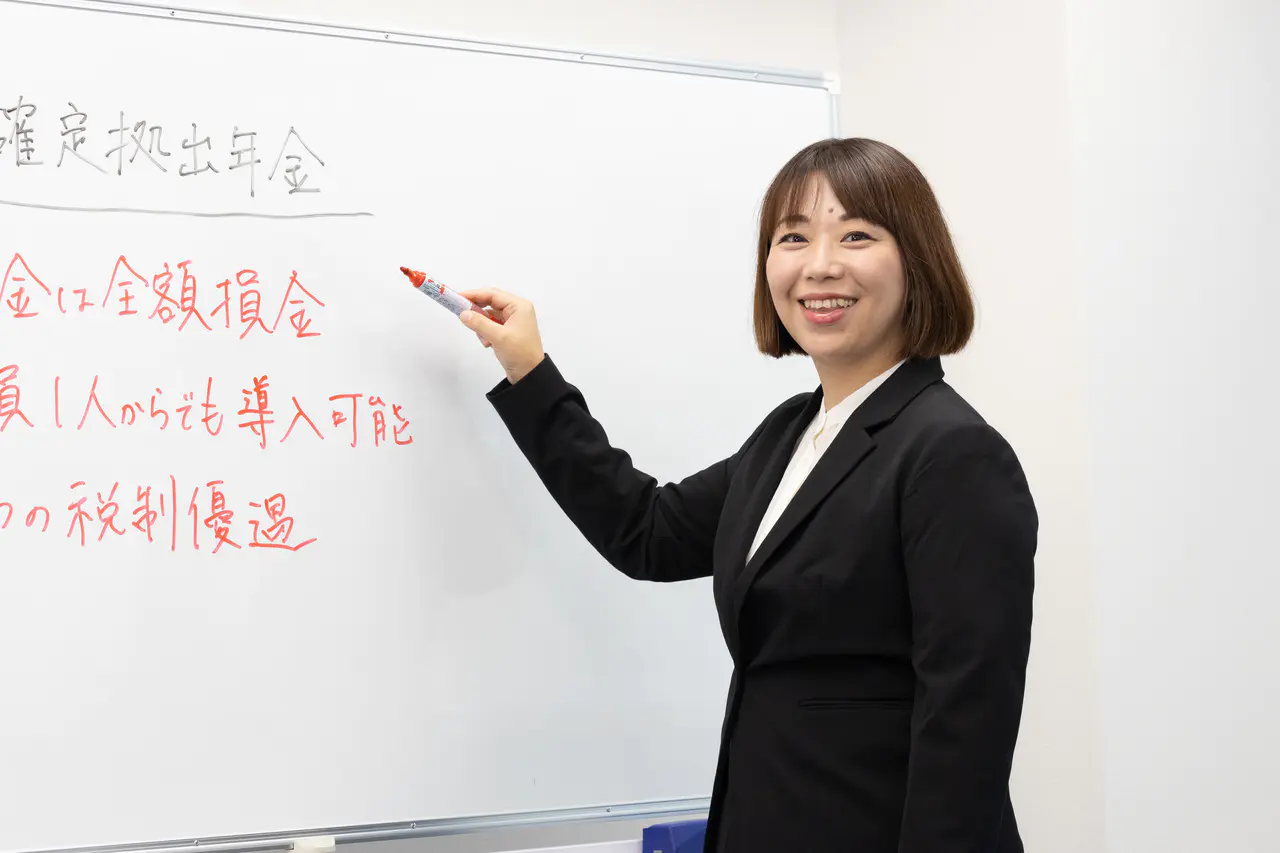
目標が明確になることで、毎月の積立額や運用方針も具体的に決められるようになります。 ここでは、自分にとって最適な目標額を導き出すための3つのステップを解説します。
このステップに沿って計算を進めることで、確定拠出年金で準備すべき金額が明らかになり、より現実的な資産形成計画を立てることが可能になります。
ステップ1:退職後の毎月の支出額を予測する
最初に、老後の生活で毎月どれくらいの支出が見込まれるかを予測します。 現在の家計簿を参考に、食費、水道光熱費、通信費、住居費(ローンの返済が終わっているかなど)、保険料といった基本的な生活費を洗い出します。
それに加え、医療費や介護費用、趣味や旅行、子どもや孫への援助など、老後ならではの支出も考慮に入れることが重要です。
現在の支出から、退職後に不要になる項目(子どもの教育費など)を差し引き、逆に増えるであろう項目(医療費やレジャー費など)を加えることで、より実態に近い支出額を算出できます。
ステップ2:公的年金など受け取れる収入額を把握する
次に、老後の収入源となる公的年金の受給見込額を確認します。 毎年誕生月に日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」や、ウェブサイト「ねんきんネット」を利用すれば、将来受け取れる年金額の目安を手軽に調べることが可能です。
自営業者か会社員か、また加入期間や納付額によって受給額は大きく異なるため、必ず自身の状況を確認してください。
公的年金の他にも、企業からの退職一時金や企業年金、個人で加入している個人年金保険など、受け取れる見込みのある収入はすべてリストアップし、合計額を把握します。
ステップ3:不足額から確定拠出年金で目指す金額を設定する
最後に、ステップ1で算出した「毎月の予測支出額」から、ステップ2で把握した「毎月の収入額」を差し引きます。 この差額が、老後の生活で毎月不足する金額となります。 例えば、月の支出が30万円、収入が20万円であれば、毎月10万円が不足する計算です。
この不足額に、老後の生活期間(例:65歳から90歳までの25年間)を掛けることで、生涯にわたって不足する総額が算出されます。 この総額が、確定拠出年金で準備すべき目標額の目安となります。

3. 【年代・利回り別】目標額2,000万円を達成するための毎月の積立額シミュレーション
老後資金の一つの目安として、2,000万円を目標額に設定した場合の積立シミュレーションを見てみましょう。

確定拠出年金は長期運用が前提であり、運用によって得られた利益がさらに利益を生む「複利効果」を活かすことが重要です。目標運用利回り(目標運用利回り)が高くなるほど、また運用期間が長くなるほど、毎月の積立額は少なくて済みます。
ここでは、年代別に65歳までの運用期間を想定し、年率3%と5%で運用できた場合の毎月の積立額を試算します。
20代から始める場合の毎月の積立額
25歳から65歳までの40年間、長期にわたって積み立てる場合、複利効果を最大限に活用できるため、月々の負担を大きく抑えることが可能です。目標額2,000万円を達成するためには、年率3%で運用できた場合、毎月の積立額は約2.1万円となります。
もし積極的な運用で年率5%のリターンを実現できた場合、毎月の積立額は約1.3万円まで減少します。早くから始めることで、少額の積立でも着実に資産を形成できることが大きなメリットです。
時間を味方につけ、コツコツと積み立てを継続することが、将来の大きな資産につながります。
30代から始める場合の毎月の積立額
35歳から65歳までの30年間で積み立てを行う場合、20代から始めるケースと比較して運用期間が10年短くなるため、同じ目標額を達成するためには月々の積立額を増やす必要があります。
目標額2,000万円に向けて、年率3%で運用した場合、毎月の積立額は約3.4万円が目安です。より高いリターンを目指し、年率5%で運用できた場合には、毎月の積立額は約2.4万円となります。
30代は収入が増える時期でもあるため、家計の状況を見ながら、可能な範囲で積立額を設定し、計画的に資産形成を進めていくことが求められます。
40代から始める場合の毎月の積立額
45歳から65歳までの20年間で積み立てる場合、運用期間がさらに短くなるため、目標達成にはより大きな月々の積立額が必要になります。
目標額2,000万円を達成するためには、年率3%での運用だと毎月の積立額は約6万円にのぼります。年率5%で運用できたとしても、月々の積立額は約4.9万円が必要です。運用期間が短い分、複利効果の恩恵も限定的になるため、スタートが遅れるほど月々の負担は大きくなる傾向にあります。

4. iDeCoよりも企業型DCのメリットが大きい理由
確定拠出年金には個人型のiDeCoと企業型の企業型DCがありますが、勤務先に企業型DCの制度がある場合は、利用を検討する価値があります。

企業型DCは、iDeCoにはない税制上のメリットや手数料の面で有利な点が多く、効率的な資産形成につながりやすい制度設計になっています。
拠出限度額が大きい
企業型DCはiDeCoと比べ、毎月の拠出可能限度額が2倍以上あるため、非常に効率よく老後の資産形成を進めることができます。※個人事業主以外を想定
iDeCo:最大23,000円
企業型DC:最大55,000円
口座管理手数料は企業負担
企業型DCでは、iDeCoで加入者が負担する必要がある口座管理手数料などの運営管理費用を、企業が福利厚生費として負担します。(※在職中に限る)
これにより、運用にかかる実質的なコストを抑えられ、効率的な資産形成につながります。
5. 目標額達成の鍵を握る運用商品の選び方のポイント
確定拠出年金で目標額を達成するためには、毎月の積立額だけでなく、どのような金融商品で運用するかが極めて重要です。

運用商品の選択によって、将来の受取額は大きく変動します。 投資初心者にとっては商品選びが難しく感じられるかもしれませんが、いくつかの基本的なポイントを押さえることで、自分の考えに合った適切な商品を選ぶことが可能です。
ここでは、目標達成の可能性を高めるための、運用商品選びにおける3つの重要な視点を解説します。
自分のリスク許容度に合わせた資産配分を考える
一般的に、年齢が若く運用期間を長く取れる場合はリスク許容度が高く、積極的にリターンを狙う株式の比率を高めることができます。
一方、退職が近い年代では、安定性を重視して債券や元本確保型商品の比率を高めるのが基本といわれています。
自分のリスク許容度を理解し、それに合った資産配分(ポートフォリオ)を組むことが、長期的な資産形成の土台となります。
コストを抑えるために信託報酬が低い商品を選ぶ
確定拠出年金は数十年単位の長期運用となるため、運用にかかるコスト、特に投資信託の「信託報酬」が最終的なリターンに大きな影響を与えます。
信託報酬は、投資信託を保有している間、継続的に発生する手数料です。たとえ年率0.数パーセントの違いであっても、長期間にわたって複利で運用すると、その差は無視できない金額になります。
同じような投資対象(例えば、日本の株式に投資するインデックスファンド)であれば、運用成績に大きな差は生まれにくいため、信託報酬がより低い商品を選ぶことが合理的な選択といわれています。
元本確保型と投資信託を上手に組み合わせる
確定拠出年金の運用商品には、大きく分けて「元本確保型」と「投資信託(価格変動型)」の2種類があります。元本確保型は、定期預金や保険商品などが該当し、満期まで保有すれば元本が保証される安全性の高い商品ですが、大きなリターンは期待できません。
一方、投資信託は国内外の株式や債券などで運用し、高いリターンが期待できる反面、元本割れのリスクも伴います。自分のリスク許容度に応じて、これらの商品を適切に組み合わせることが重要です。
6. 運用を始めた後に欠かせない定期的なメンテナンス
確定拠出年金は、一度運用商品を決めて積立を開始したら終わりではありません。

目標額を達成するためには、定期的に運用状況を確認し、必要に応じて見直しを行う「メンテナンス」が不可欠です。
市場環境は常に変動しており、当初の資産配分が時間とともに崩れていくことがあります。 また、自身のライフプランの変化によってリスク許容度も変わる可能性があります。
長期にわたる資産形成を成功させるためには、定期的な評価額の確認と計画の見直しを習慣づけることが大切です。
年に1度は運用実績を確認する習慣をつける
忙しい日々の中で運用状況を毎日チェックする必要はありませんが、少なくとも年に1回、できれば自分の誕生月など忘れにくいタイミングで運用実績を確認する習慣をつけましょう。
運用会社から送られてくるレポートやウェブサイトで、現在の資産評価額や損益状況、各商品の運用成績などを確認します。 当初立てた目標に対して順調に進んでいるか、想定よりもリターンが低い、またはリスクを取りすぎていないかなどをチェックします。
現状を把握することで、次のアクションを考えるきっかけになります。
ライフプランの変化に応じて運用計画を見直す
結婚、出産、住宅購入、転職、昇進といったライフイベントは、家計の状況や将来の計画、リスクに対する考え方を変えるきっかけになります。
例えば、子どもが生まれたことで、より安定的な運用を重視するようになるかもしれません。 また、収入が増えたことで、より積極的にリスクを取れるようになる可能性もあります。 このようなライフプランの変化があった際には、現在の資産配分が自身の状況に合っているかを見直すことが重要です。

7. まとめ
確定拠出年金における目標額の設定は、老後資金形成の羅針盤となる重要なプロセスです。
まず老後の支出と収入を予測して必要な資金額を算出し、それを基に具体的な目標を立てます。

目標達成のためには、年代やリスク許容度に応じた積立額と運用利回りを想定し、計画を立てることが不可欠です。 特に企業型DCは税制面などで有利な点が多く、制度がある場合は積極的に活用すべきです。
商品選択では、リスク許容度に合わせた資産配分を考え、信託報酬のようなコストを意識することが求められます。
そして、運用開始後も年に1度は運用状況を確認し、ライフプランの変化に応じて計画を見直す定期的なメンテナンスが、目標達成の確度を高めます。
日本企業型確定拠出年金センターでは、企業担当者のみなさまに、導入に関する個別相談を無料で行っています。導入時期についてもご相談を承っていますので、ぜひ一度お問合せください。
よくある質問
Q 記事にあるような「目標額の計算」などを、会社が従業員に教える必要がありますか?
A 法令上、会社には「投資教育」の努力義務がありますが、専門的な内容は外部委託が可能です。
記事にあるようなライフプランの考え方や商品選びのポイントを、経営者様や担当者様がすべて教えるのは大変です。導入時の説明会や継続的な教育サポートを行っている専門機関にお任せいただくのが一般的です。
Q 役員も企業型に加入できますか?
A 70歳未満の厚生年金保険被保険者であれば、役職に関係なく社長や役員でも加入できます。※就業規則や制度設計によります。
もちろん、掛け金は全額損金計上できます。拠出限度年齢の引き上げを行った場合は拠出限度年齢まで加入できます。
Q iDeCoと比べて、会社が企業型DCを導入するメリットは何ですか?
A 会社は掛金を「全額損金」で積み立てでき、従業員は口座管理手数料の負担をすることなく資産形成ができる点です。
お問合せ・ご相談はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:050-3645-9040
※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。




















